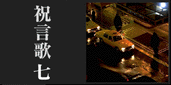「いや〜ん、リュミちゃん。かーわいい〜!!!」
オリヴィエの嬉々とした声が反響する。
リュミエールは目の前に鏡が無いを不幸中の幸いと思うことにした。彼はオーガンジーが幾重にも重なる、それは華やかなドレスに身を包みながら、やるせない想いと闘っていた。
このステージ裏の倉庫は例のファッションショーの為に設けられたものだった。ショーでモデルによってライトを浴びるはずの作品が所狭しと置かれていたのだ。あまりに中が暗かったので気付かなかっただけだ。手近な明かりを灯してみると、そこかしこにきらびやかな服が浮かび上がる。さすが、オリヴィエチェックの入るデザイナーの作品だ。溢れる色、色、色。
「やっぱねえ、オスカーとかリューイは少し無理あるけどね、リュミちゃんは全然イケてるわ〜。女顔だからねえ。ま、私のスタイリングもまた良いんだけど。どうせだからこのウィッグも付けてー。うん、良い、良い!」
「ほんと、モデルさんみたい、リュミエール」
やはりここは女の子ならでは、真面目に感想を述べるケイ。今までの生活とは無縁だったろう美しい衣装を目の前にして、彼女は素直に顔をほころばせている。そんな笑顔を見るのは、リュミエールにとっても嬉しいことだったし、この状況の中では唯一の救いだった。ふと、この悲惨な状況に何も言わずにいる二人に目をやる。オスカーとリューイは、あまりに気の毒で正視できない、と言ったようにリュミエールから目をそらし傍観を決め込んでいた。彼等はドレスを着るには少し無骨だという理由で、派手ではあるがメンズの服をあてがわれ、女装は免れた。オリヴィエ渾身のコーディネートによってどこから見ても女性にしか見えないリュミエールには、彼等がとてつもなく羨ましく思えた。
「これだけ変装すりゃ、取りあえず追手の目をごまかすことはできるな」
目を閉じ、何かにじっと堪えているリュミエールを横目に、オスカーは言った。
「ね、名案でしょ〜〜〜〜自分の頭の回転の良さに恐れ入るわ〜」
オリヴィエはうっとりと自分の服に目をやった。
「・・・・とにかく、早く行きましょう・・・・」
呟くように、リュミエールが言った。一秒でも早くこの状況から解放されたい。
「ちょっと待って!せっかくだから少々」
オリヴィエが倉庫の奥まで駆け出し、あれやこれやと物色を始めた。
「・・・オリヴィエ!あなたは事の重大さがわかっているのですかっ!!!!」
リュミエールの顔は青ざめ、その絶叫は怒りに震えていた。
 祭の群衆の中でも一段と目を引く一行だった。しかし、これもイベントのひとつかと皆勝手に納得するのか、指さし眺めながらも彼等を見とがめる者はいなかった。警備の者でさえも、快く道をあける。特にリュミエールの美しさには、皆一様に羨望の眼差しを向けた。リュミエールは堪えた。これもケイとリューイの為・・・・。
祭の群衆の中でも一段と目を引く一行だった。しかし、これもイベントのひとつかと皆勝手に納得するのか、指さし眺めながらも彼等を見とがめる者はいなかった。警備の者でさえも、快く道をあける。特にリュミエールの美しさには、皆一様に羨望の眼差しを向けた。リュミエールは堪えた。これもケイとリューイの為・・・・。
王立研究院の分院まではそう遠くなかった。都市部から少し離れたところにくだんの建物の高い塀はそびえ、その門は祭などとはまったく無関係な顔で堅く閉じられ、外界を遮断していた。
リューイは未だここに来る意味が理解できなかった。王立研究院の分院など、その星の要人でさえ無闇に中に踏み入ることはできない治外法権の場所だった。何の迷いもなくここへ来るこの3人・・・ただの観光客などではない。一体何者なんだ?ケイもまた同じ思いを抱いているらしく、不安そうにただリューイを見つめていた。
門の前に立つと、その重く厚い扉がゆっくりと開かれる。内にはうやうやしく頭を垂れる研究員達がずらり並んでいた。その中の一人が口を開く。
「お目にかかれて光栄でございます。オスカー様、オリヴィエ様、リュミエール様。そして御友人の方々。ご連絡を受けた時は驚きました、まさかこの星にいらしていたなど」
「すまんな、ないがしろにしたつもりはないんだが」
オスカーの口調はいつもの調子と何ら変わりは無かった。が、リューイとケイの目には今までいた彼とはまったく違う人物にすり替わったのではないかと思われるほど、その姿が威厳に満ちたものに見えた。
「いいえ、お気遣いなさらず。先刻、ルヴァ様が次元回廊にてお出まし、お待ちでごさいます」
「いろいろお世話をかけて申し訳ありません。では中へ急ぎましょう」
先程まで所在無く皆の後ろに隠れるようにしていたリュミエールが、一同を促した。
「おやおや、まーまーあなたがた。その格好はいったいー」
守護聖達の扮装を見るやいなや、地の守護聖は呑気な台詞を吐いた。
「こ・これはその・・・・」
「かーわいいでしょー?私のお見立て。ルヴァもやって欲しい??」
赤面するリュミエールを無視し、オリヴィエがふざける。
「えー私は遠慮しますよー。でもわかりました、リュミエールがいつもの衣装を何を置いても持って来て欲しいと言った訳が」
「あの非常時にそんなこと言ってたの?あんたってば」
「あの非常時にこんなことさせたのはオリヴィエ、あなたでしょう」
「まーまー、喧嘩はいやですよー。とにかく着替えてきたらどうでしょうかー」
相変わらず呑気な調子のルヴァだ。彼は3人よりもずっと先輩にあたる守護聖なのだが少しもそんなことは感じさせない。しかしだからといって見下されているというようなこともなく、彼の持つ膨大な知識、そしてそれを鼻にかけたりしない柔和な人柄のため、皆の尊敬と信頼を集めているのもまた事実だった。
3人が部屋を後にし、場にはケイとリューイ、そしてルヴァだけが残った。
リューイが神妙に聞く。
「あの・・・・これは一体どういうことなのでしょうか。俺達、やつら・・いえ彼等の素性を何も知らないんです」
「ああ、それでは驚かれたでしょうね。彼等、私もですが、実は守護聖と呼ばれる立場の者です。ご存知でしょうか?」
「・・・守護聖?あの、女王陛下にお仕えする?」
ケイが即座に聞き返す。
「あたし・・・本当にいるなんて知らなかった・・・・」
ルヴァがにっこり微笑みを投げかけた。
「そうですね、星によっては神格化されすぎて架空のものだと思っている人も多いみたいですね。でもいるんです、女王陛下も守護聖も」
「・・・・・・・・・」
リューイはただただ唇を噛んで黙っていた。頭をこれまでの出来事が巡る。屈託のない彼等の笑顔、普通と何ひとつ変わらぬその言動。なのに、守護聖?
その時、3人が身支度を整えて戻ってきた。ケイとリューイはその姿に目を奪われたまま、逸らすことができなかった。
「どーしちゃったの〜、ケイ。おっきなお目目がさらに倍!顔からこぼれ落ちそうだよ」
オリヴィエの軽口にもすぐさま反応できない。ケイの目に映る3人はそれは神々しく、華やかで近寄りがたかった。今までのように気軽に話などできなかった。
ルヴァが二人に向かって言った。
「私達も聖地に戻らねばなりませんので、そうゆっくりもしていられません。お二方の為に小型の高速シャトルを用意しました。それで事が沈静化するまでどこか遠くへいらっしゃると良いかと・・・。この星以外でも可能ですよ。では、私は次元回廊の準備がありますので、失礼します。では、お気をつけて」
そう言って地の守護聖は部屋を去った。
ルヴァが去った後、なんとも言えぬ気まずさが場に漂っていた。
「黙っていてすみませんでした。騙すつもりは無かったのです。ただ言わない方が・・」
「リュミエール、そんな言い方したら二人がよけいに硬直するだろう」
オスカーが優しく続ける。
「ケイ、リューイ。俺達はこんな身の上だが、ひととき自由な時間を過ごせたのは二人のお陰だ。ありがとう」
ケイとリューイの二人は、まだ言葉をみつけられないのか、ひたすらに黙っている。存在すら架空のものと思っていたような、神にも等しい人々と今まで一緒にいたことが、未だ実感として湧かないのだった。呆然として立ち尽くしている。
「やーねえ、いつもの元気はどしたのよ?頼むからそんな顔しないで」
ケイの小さな肩を、ぽんっと叩きながら、できるだけこの空気を和らげようとするオリヴィエだった。
ケイがやっとの思いで言葉を発した。
「なんか・・・・いろいろ失礼なこと・・・・してたけど・・・・」
ごにょごにょと呟くように言い濁す。しかし、意を決したのかうつむいたその顔を上げた。
「ごめんなさい、そして本当にありがとう」
「俺も・・・ケイに同じくだ。あんた達・・あ・・もういいや、あんた達に出会えなかったら、あのままずっとつまらない事にこだわってなきゃならなかった。本当に感謝してる。この出会いのお陰で、俺達は新しい道を見つけることができた」
リューイの瞳は強い意志を持って語る。
「新しい道ってのはなんだ?他の星で一からやり直すのか?」
そうオスカーが問う。
「違うでしょ?リューイ。私達の故郷はここだから。他の星へ逃げたりしない」
「ああ。さっきの人が他の星へ言ってもいいと言った時、俺は、いや俺達は、この星を何よりも大事に思ってることに気付いたんだ。他に行く場所はない。ここで、俺達が作るこの星の未来を、やっぱりこの目で見届けたいんだ」
ふとケイはリュミエールを見た。この守護聖との出会いがこの想いを生んだ。しかし彼は少しだけ寂しそうな表情をしている。その理由をケイはわかっていた。
「心配しないで、リュミエール。もう爆弾仕掛けたりなんてしないから。私達は私達のやり方で、この星に関わっていくわ。権力を握りたい訳じゃない。捨て石だってかまわないの。いずれ、この星が苦しい時代を抜ける時が来ればそれで」
ケイとリューイの今の素直な気持ちを、守護聖達は心静かに聞いていた。出会った初めの、あのささくれだった雰囲気が消えて、今の彼等は何かを乗り越えた。単なる感傷から一歩ぬきんでたその顔は、いきいきと輝いていた。
「そんな心意気に・・・俺の炎のサクリアが届くように祈ってるぜ。この先、どんな困難に出会っても決して挫けぬよう、強くいられるように」
オスカーが言った。オリヴィエが続ける。
「じゃあ、アタシは夢のサクリアね。その胸に抱いた最初の夢を忘れずにね。いつまでもピュアでいられたら、きっと叶う。遠くから、でもいつもいつも、アタシの力があんた達に届くよう想い続けてるよ」
ずっと黙って事の成りゆきを見ていたリュミエールが、最後に口を開いた。
「では私は『優しさ』を・・・。いついかなる時も他を思いやる心を忘れずにいられれば、あなた方の志はきっと美しい結晶となってこの星を照らすでしょう。どんな時も、自分と等しく多くの者達の幸福を願っていてください。私のサクリアがいつまでもあなた方を守りますように・・・・・・・・」
しばしの間沈黙する一同。誰もが喉まで出かかった最後の言葉を持て余していた。ほんの短い間でも確かに彼等の間には何かが生まれていた。別れ難い思い。とりたてて何か特別な事があった訳ではないのに、長きに渡っての友人のようにお互いが思われた。
いつまで経ってもキリがない。リューイが意を決して言った。
「オスカー、オリヴィエ、リュミエール。俺達もう行くよ。これ以上いても余計辛くなりそうだから。いろいろありがとう。もう会うことは・・・無いと思うけど。元気で」
「本当に、ありがとう・・・一生忘れない、今日のこの日のことは」
ケイがその大きな目から涙をこぼしながら呟いた。
「あ、なんかリュミエールの前で泣いてばっかりだね、私」
無理に笑顔を作る彼女がけなげだ。リュミエールは静かにその涙を指で拭った。
「ケイ・・・これから行くあなたの道はきっと平坦なものではないでしょう。でも、今までとは違います。この先は、あなたには泣く場所がある、リューイという名の」
「リュミエール・・・・」
「いつまでも二人仲良くいてくださいね。妹のようなあなた・・・この兄はあなたの幸福を心から祈っていますよ」
せっかく拭った涙が、再び溢れ出す。思わずリュミエールに抱きつくケイ。子供のように泣きじゃくる彼女を、周囲の男達はただ無言で見守っていた。
「それじゃ、行くね」
ケイが涙で赤く充血した瞳をせいいっぱい開きながら、ぺこりと頭を下げた。リューイもそれに倣い頭を下げ、そしてケイに寄り添うように歩きだそうとした。
「ちょっとまって〜〜〜〜〜〜〜!!!!」
部屋の奥から何やら大きな包みを持って来るオリヴィエ。
「ちょっとがさばるけどね、ま、シャトル移動だし。これプレゼント!持ってって頂戴」
「プレゼント・・・・?」
「本当は時間さえ許せば私がデザイ・・・いや何でもない・・・中身は後のお楽しみにしてね。じゃ、気をつけて」
オスカーとリュミエールも口々に別れの言葉を次いだ。彼等はいつまでも名残惜しそうにこちらを振り返りつつ、シャトルに乗り込むため、部屋を後にした。
思いのほか長い別れだった。きっと待ちくたびれているだろう、ルヴァの元へ3人も急いだ。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |
 祭の群衆の中でも一段と目を引く一行だった。しかし、これもイベントのひとつかと皆勝手に納得するのか、指さし眺めながらも彼等を見とがめる者はいなかった。警備の者でさえも、快く道をあける。特にリュミエールの美しさには、皆一様に羨望の眼差しを向けた。リュミエールは堪えた。これもケイとリューイの為・・・・。
祭の群衆の中でも一段と目を引く一行だった。しかし、これもイベントのひとつかと皆勝手に納得するのか、指さし眺めながらも彼等を見とがめる者はいなかった。警備の者でさえも、快く道をあける。特にリュミエールの美しさには、皆一様に羨望の眼差しを向けた。リュミエールは堪えた。これもケイとリューイの為・・・・。