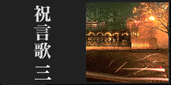「で?どーーーーーーーしてもそれ、あの子に返したいって言うのね?」
リュミエールは頷いた。
「お世話になった方のものです。お返ししなければ」
手の中にある古い水筒。到底高価なものとは思えない。しかしところどころに直したり補強したりした跡が見てとれる。きっと大切な品に違いない。
「そんなコキタナイ水筒のひとつやふたつ、別に気にしないと思うけどぉ」
オリヴィエは憎まれ口を叩きながらも、この優しげな風貌の守護聖が、一度言い出したら聞かない頑固者だということを重々知っていた。やれやれ、と肩をすくめる。
「まあまあ、オリヴィエ。そう言うな。リュミエールの気持ちもわからないでもない」
オスカーが仲裁に入る。
「ただ一つ問題なのは、持ち主の命の恩人が、どこにいるかわからないってことだ」
「そうよ、どーやって返す気よ。発信機でもつけといたって言うの?」
リュミエールの表情が暗くなった。彼等の言うとおりだ。少年の名さえ聞かなかった。これではいくらなんでも探しようがない。それはわかっているのだが、どうしても諦めきれなかった。
「そういえば・・・ショーはどうなったんです?」
「ショー?中止よ、中止。だって爆破されたの、ショーのための特設ステージだったんだもん。どうせやるなら他のとこにしてくれればいいのに」
「なかなか頭がいいぜ、この星の過激派は。まだショーが始まるには間があったからな、けが人無しで効果絶大。ステージは誰の目もひく場所にあったし」
この星は日頃から、政府と、そのやり方に反発する過激派とが激しい攻防を繰り広げているらしかった。この祭も、大統領の就任10周年を記念するものだったので、格好の標的となったらしい。爆発と同時刻に、犯行声明も出されている。
「政情不安ならさ、そんな祭、呑気にやってる場合じゃないってのわかんないのかしら」
「そういう事がわからん奴等だから狙われるんだろ、過激派にも」
「過激派、の仕業なのですか」
気付けば、リュミエールはこの騒ぎの原因をなにひとつ知らなかった。
「ああ、そうらしい。俺達、お前さんを探すんで、いろいろ聞き回ってたからな。変なことに巻き込まれてやしないかと思って心配したんだぜ」
リュミエールと彼等が離ればなれになっていたのはさほど長い時間ではなかったはずだ。それでこれだけの情報を彼等が得ていることを、ただただ感嘆するリュミエールだった。
「過激派のアジトさえわかりゃな、話は早いんだが」
オスカーがため息をつく。
「そんなもんわかってどうすんの?説教でもしにいくわけ、俺のナンパをよくも邪魔したな〜とかってさあ」
きゃはは、とオリヴィエが笑い声を上げる。
「話が早いとは?」
悪ふざけするオリヴィエを無視し、リュミエールが聞き直した。オスカーは逆に、なぜそんな質問をするのかといいたげな表情をした。
「お前が言い出したんじゃないか、水筒返しに行きたいんだろ?」
リュミエールもオリヴィエもまだオスカーの言葉の意味がわからない。
「まさか気付かなかったのか?」
仕方のない奴等だと肩をすくめながら彼は言った。
「彼女、過激派の一味じゃないか」
「過激派?」
「彼女?」
オリヴィエとリュミエールが同時に声を上げた。
「あの、少年が女性だと言うのですか?」
リュミエールはさっきまで目の前にいた少年の姿を思い起こしていた。今にして思えばあの線の細さ、小柄な風体は女性のものだったかもしれない。あんなに間近にいたのに気付かなかった。ましてやオスカーは一瞬しか目を合わせなかった筈だというのに。
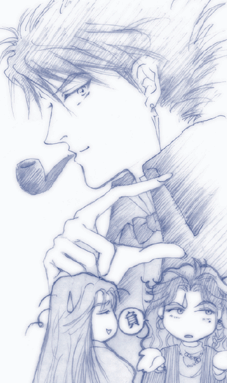 「で、なんで過激派だってわかるのよ」
「で、なんで過激派だってわかるのよ」
オリヴィエはまるで探偵の種明かしを聞くように興味津々だ。オスカーはさも自慢げに胸をはる。
「俺は一回会ったレディは忘れないのさ」
一回会った・・・・。
「あ!指名手配書!!!」
「オリヴィエ、ご名答」
空港に貼られていた一枚の指名手配のポスター。確かにそこには過激派一味の写真があった、あったけれども。
「警察犬じゃあるまいし・・・・・」
「あ?なんか言ったか?オリヴィエ」
「なんでもなーい!」
あの少年、いや少女が過激派とわかったところでおかれた状況が何ら変わるわけではなかった。近くを通り過ぎる人々にそれとなく聞いてみたりもしたが、警察でさえ喉から手が出るほど欲しがっている過激派の情報なぞ、そうそう教えてくれる通行人などいる訳もない。
「こんなとこで3人で額付き合わせてても仕方がない。ちょっと店でも入らないか」
オスカーが提案した。他の二人もその意見に賛同し、少し歩きまわり、ひっそりと営業していた裏道の目立たぬ居酒屋のドアを開けた。
中には数人の客が、店の主人と会話を交わしつつ、酒を飲んでいた。が、何か雰囲気が堅い。祭があんなことになって客も消沈気味なのだろうか。客達が一斉に注ぐ3人への視線も、なにやらきつい。
手近な空席に腰を落ちつけると、でっぷりと太った主人がうやうやしく、かつ空々しい笑みを浮かべて歩み寄ってきた。
「いらっしゃいまし。何になさいましょう?」
「とりあえず酒と、何かつまみを頼む」
オスカーは端的に用件だけを述べた。いつもの彼なら軽い世間話のひとつも言うところであったが、とてもそういう雰囲気ではなかった。
「・・・なんかヤバイ店っぽくなーい?」
オリヴィエがそっとリュミエールに耳打ちをする。
「オリヴィエ、そのような。きっと常連が多いお店なんでしょう」
不用意な発言が周囲に聞こえやしないかと、より一層声をひそめてリュミエールは返事をした。
その時、また新たな客が二人ほど店に入って来た。店の客達の視線が一斉にそちらに行く。3人も、ついつられてそっちを見やった。
「あ!お前らっ!!」
入って来た人物の一人が、3人の方を見て声を上げた。
「ボス!コイツら、さっき人混みの中であれこれ俺達のことを聞きまわってたんですぜ!」
その言葉を聞いて、店の客達が瞬時に腰を上げる。
「何?」「警察か?」「つけて来やがったのか?」
口々に発する台詞は、不穏な緊張を帯びていた。
状況を総合し察するに、この店はこの3人がこれから探し当てようとしていた場所にもっとも近い所だったということだ。
「あ〜〜〜〜らら、ここってば過激派の集会所だったの」
オリヴィエがさして動じず呟いた時にはもう、3人は店中の者に取り囲まれていた。
そして奥にいた店の主人、ボスと呼ばれたその人物はさっきと同じ笑顔で言った。
「そこまでご存知なら、とりあえず同行してもらわなきゃならないな」
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |
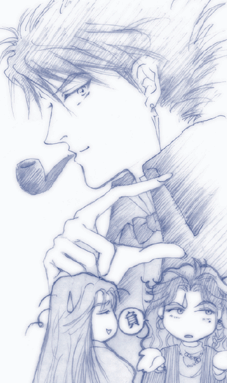 「で、なんで過激派だってわかるのよ」
「で、なんで過激派だってわかるのよ」