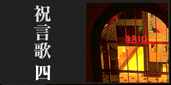「すみません・・・・このようなことになるとは・・・・」
リュミエールは、他の二人に言った。
3人は店で捉えられ、過激派のアジトらしき家に連れて来られた。さして大きくもないその屋敷の二階の一室に、彼等は押し込まれているのだ。
オスカーは勿論、オリヴィエも腕には覚えがある。その気になれば逃げられぬことはなかった筈だが、敢えて抵抗せずにいたのを、リュミエールは自分の為と知っていた。
「気にしないでいい。手間がはぶけた」
「ま、ちょっと予想外だったけど、なんとかなるでしょ。ちょっとわくわくもするし〜」
二人とも、いつも通りだ。リュミエールを元気づけようとして言っているのではなく、本気でそう思っているのだから、神経が太い。
「随分余裕があるんだな」
部屋の奥から男の声がした。人の気配なぞみじんも感じなかった3人は驚いた。声の方向を見ると、大あくびをしているまだ少年の匂いを残した若い男。見た所17、8歳か。
「こんなのにナメられてるよーじゃ、しょうがねえなあ」
若者は誰に言うでもなく呟くと、椅子に座ったまま、かったるそうに3人を見た。
「まったくボスも暇だよ。こんな余所者にかまってる暇があったらやることあるだろうに」
どうやら仲間であることは間違いないらしいが、今までの過激派達の、ひりつくような敵意は無い。3人に対してもさほどの興味も無いようだ。
「リューイ!そんなこと言ってるの聞かれたら、またつつかれるわよ」
部屋のドアはいつのまにか開いていて、そこには人が立っていた。
「ああ!あなたは」
リュミエールが思わず驚きの声を上げる。そこにいたのはまさにこの事態の原因たるリュミエールの探し人だった。こんなに都合よく会えるとは。彼女もまたリュミエールの姿を見て同じように驚いている。
「あ、掴まったのってアンタの事だったの?まさか・・・政府の回し者・・・な訳ないよね。あんなに鈍くさかったんだもの」
彼女は思い出し笑いに、小さな身体を大きく揺らした。
「勿論です。ただあなたにこれを返したくて、いろいろ聞き回っていたら勘違いされてしまったのです」
リュミエールは例の水筒を彼女に差し出した。小さな手がそれを受け取る。彼女はすでに笑ってはいず、神妙な面もちで礼を述べた。
「あー、ありがとう。・・・それじゃ災難だったわね。みんな今ぴりぴりしてるから、ちょっと怪しいってだけで引っ張ってきちゃったんだわ」
「ケイ、知り合いなのか?」
やりとりを眺めていた、リューイと呼ばれた若者が言った。
「知り合いって程でもないよ。祭の人混みでちょっと会っただけ。また会うことになるなんて思わなかった。あたしはケイ。こっちのはリューイ。アタシ達が何者かは・・もうわかってるよね」
リュミエールは頷き、自分とともに同行の二人のことを簡潔に彼女に紹介した。勿論、守護聖だということはふせて。主星から祭見物にやってきただけの観光客なのだ、今は。
改めてケイという名の少女を眺める。こうして明るいところで見れば、少年には見えない。どころか、小さく丸い顔に大きな瞳が愛嬌のある、可愛らしい顔立ちだ。髪も短くスレンダーな体つきであっても、今なら間違うことはないだろう。あの時とくらべて瞳の光がいささか柔らかだからかもしれない。
「で?首尾はどうだったんだ?」
3人の存在など意に介さず、リューイはケイに話しかけた。リューイはどうやらずっとここにいて、爆破現場には行っていないようだ。
「うん、派手にぼーんっとね。くだらない祭は即刻中断。いい気味」
ケイはふふっと軽く笑った。殺伐とした会話であるのに、その笑顔は愛らしい。
「今回ちょっと中身変えたからいつもと威力が違ったろ?被害は?」
「ばかでっかいステージが一個壊れた。あとはそこそこ。人出が多かったから、パニックになってちょいと軽くケガ人出たみたいだけど」
「ふーん・・・・・」
リューイはケイの言葉に肯定的とも否定的ともとれない表情をした。
どうやら、爆弾はこのリューイが作ったものらしい。気付けばこの部屋にはそこかしこに機械類や工具類がおいてある。作業場のようだ。
ケイは3人の方に向き直った。
「リュミエール。わざわざ届け物ありがとうね。でもここから帰るにはボスに説明しなきゃね・・・・今しがたでかけちゃったのよ。ちょっと待って貰える?」
「それはかまいませんが・・・すみません、なんだかご迷惑を」
間違えられて迷惑を被っているのはどちらかといえば3人の方なのだ。なのにやけにすまなさそうにしているリュミエールを見て、オリヴィエとオスカーは少し呆れ顔をした。
「オヤジさん、また呼ばれたのか?」
「うん。なんだか渋い顔してたから多分あんまりいい話じゃないね。また上の方からせつかれてるのかも」
上の方、ということはこの過激派グループはどこかに所属しているのか。確かに一国の政府をひっくり返そうとするのには人数が少なすぎるように思われた。オスカー、オリヴィエ、リュミエールの3人は二人の会話から少しずつ情報を得、置かれた状況をより明確にしていった。
 「なんでお前さん達みたいな子供が反政府運動なんかしてるんだ?」
「なんでお前さん達みたいな子供が反政府運動なんかしてるんだ?」
今まで黙っていたオスカーが単刀直入な質問を浴びせた。リュミエールもオリヴィエも同じことを思っていた。
「子供扱いとは失礼だな。・・まあ主星なら呑気に学校でも行ってる年か。あいにくこの星でそんなにのんびりしてるのは、中央に住んでる裕福な奴等だけだ」
リューイは、オスカーを睨みつけ、きつい調子ではき捨てるように言った。
「ちょっと都会から離れれば、字も読めない大人がごまんといる。ろくな仕事もなくて、今日食うにも困ってる。主星からわざわざ物見遊山に来てるお方には信じられないかもしれないけどな。あんた達が落としてく金はみんな政府のお偉いさんの懐に入って、私腹を肥やすだけ。言うなればあんた達も政府側に荷担してる、俺達の敵だ」
話しているうちに怒りがわき上がってきたのか、少年の声が次第に荒い。
「政府の大事な金ずるになんかあったら、奴等青くなるだろうなあ。ボスに今更間違いだったから帰らせてくれっていっても無理かもしれないぜ?」
「リューイ!」
子供をたしなめる母のような口調で、ケイが言葉を遮る。
「・・・ごめんね、みんな。そんな事にはならないよ。関係の無い人を巻き込むのは反政府運動とは違う。あたし達の敵はあんた達じゃない。リューイだってわかってるでしょ?」
不満げにふてくされるリューイを見るケイは少し寂しげだ。
「いろいろあるみたいだねぇ。若いのに大変だ」
しばしの沈黙の後、こわばった雰囲気を和らげようとしたのか、オリヴィエが独り言のように言った。
平穏な聖地に長くいると、ともすれば忘れそうになるが、この二人のような若者がこの宇宙には多くいるのだろう。平和で豊かな星ばかりではない。
こんな事実に出会う度に、守護聖という立場に彼等は無力感を覚える。それぞれ持つ聖なる力を、直接行使することは許されていない。今目の前に自分の力を望む者がいたとしても。この星の、この程度の争いを止めることなど彼等の力を統べる女王にとっては造作も無いこと。しかし、目に見えた救いの手を差し延べることは、甘えを生み、自立を妨げる結果を招く。それでは統治とは言えない。
自分の身に満ちる力を自覚しながら、どうすることもできない。その葛藤に打ち勝つことこそが、守護聖に求められる最初の試練だった。守護聖の任についたばかりの頃は耐えきれない痛みを伴ったものだったが、いつのまにか慣れてしまった。激痛は小さな苦痛に変わり、いつしか日々に紛れていく。鈍感にならなければ到底堪えていけるものではないと言い聞かせながら、それでも一抹の空虚をどうすることも出来ずに胸に抱き続ける。この目の前の若者達に、その苦しみを伝えることさえ叶わないのだ。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |
 「なんでお前さん達みたいな子供が反政府運動なんかしてるんだ?」
「なんでお前さん達みたいな子供が反政府運動なんかしてるんだ?」