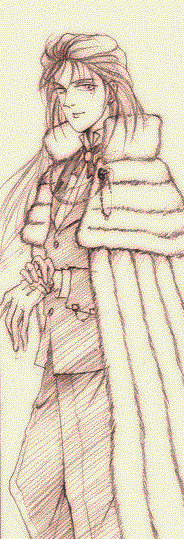

「おはよ!アンジェリーク!昨日はあれからよく・・・眠れなかったみたいね・・・・」
オリヴィエはとっさにうつむいた。笑いを必死でこらえているのだった。
アンジェリークの顔は不眠と泣き疲れでむくみにむくんで腫れ上がっていた。
「ひ・ひどい、オリヴィエ様!笑うなんて!」
「ご・・・ごめんアンジェリーク。私のせいなのにね。でも、これはちょっと酷い・・・せっかくの可愛い顔が台無し。ちょっと私の部屋においで。とにかく、冷やした方がいいわ」
オリヴィエの部屋に向かう途中も、ずっとオリヴィエは笑いをかみ殺していた。そんな様子に憤慨もしたアンジェリークだったが、それよりも安心の気持ちの方が強かった。
(良かった・・・オリヴィエ様。元気みたい。夕べのことはお酒のせいで、よく覚えてないかもしれない!・・・こんなに笑うこともないとは思うけど、気まずくなるよりはずっとマシだわ)
オリヴィエの部屋で、アンジェリークは天井を仰いでされるがままになっていた。オリヴィエはまるで手術に集中する医者のように、何やらいろいろなものを染み込ませたパックを彼女の顔一面に張り付けている。
「このまましばらく動かないでね〜、十五分もすれば少しは効果があらわれるはずだから。ごめんね、アンジェ・・・・」
「オリヴィエ様があやまることなんて何もないです!私が勝手に眠れなかっただけですから」
「ねえ、アンジェ。お詫びと言っちゃなんだけど、今晩、デートしない?まあ、この星、行くとこなんて何もないけど、夕食がてら」
「えっ、嬉しい!実は私、外行ってみたかったんです。明日には聖地に戻らなきゃだし、探査基地で終わっちゃうの寂しいなって思ってたんです。嬉しい、嬉しいです!」
オリヴィエはいつもの優しい笑みを浮かべながら言った。
「そんなに喜んでもらえるなんてね。じゃあ、こっちもきっちりエスコートするわ。・・・・勿論、今日はアルコールはヌキでね」
「はいっ!」
「は〜い、アンジェ、迎えに来たよ!仕度はできた!?」
ドアをあけると、タキシードに見事な毛皮を羽織ったオリヴィエが立っていた。それは美を司る守護聖に相応しく、誰よりも美しく凛々しい姿で、アンジェリークはしばらく見とれて立ち尽くした。
「やーだ、どしたの?口あけちゃって。・・・・良かった、顔の腫れ、すっかりひいたね。私がプレゼントしたドレスもよく似合ってる。うん、最高に可愛いよ。さ、行こうか!」
そういってオリヴィエはうやうやしく彼女の手の甲にキスをした。
「きゃっ!あっ・・・すいません、私、こういうの慣れてなくって・・・」
クビまで真っ赤になったアンジェを見て、またオリヴィエは幸せそうに目を細めた。
二人はアヌーシュカの中央、と言っても主星などから比べるとあまりにもささやかな街に行き、そこで小さいながらも雰囲気の良いレストランで食事をとった。これまでの基地での食事はかなりレベルの高いものであったけれども、それでもここで取る夕食はまた格別なものであった。二人思いっきりドレスアップして向かい合っている、というだけで、アンジェリークにとっては夢のような出来事だった。
「今夜でこの星ともお別れね、アンジェ」
「ええ・・・。少し寂しいです」
「寂しい?あはは、この星に来てそんなこと言う人、きっとアンタだけだよ。みんな最後は退屈に飽きてせいせいして帰るってのに」
「オリヴィエ様の故郷の星だってだけでも、私にとっては特別でした。やっぱり・・・寂しいです」
「そっか・・・そうね。ありがと、アンジェ。そう言って貰えて、私もなんだか嬉しいよ。こんな私にも少しは故郷を愛する心があるのかしらね。・・・そろそろ、行こうか。帰りは少し歩こう」
オリヴィエに促されて店を出ると、そこは冴え冴えとした冷えた空気が張りつめていた。空調のきいた基地や屋内では到底想像もつかない、肌を刺す空気。
「寒くない?もしあれなら、迎えを呼ぼうか?」
「大丈夫です、オリヴィエ様。私も少し歩いてみたい。それにオリヴィエ様が選んで下さったこのコート、やっと着れたんですもの、嬉しくて!」
「あはは、本当に嬉しいことを言ってくれるね、アンタって子は」
しばらく談笑しながら歩いていた、その時だった。空に、一瞬すうーっと刷毛ではいたような薄いオレンジの光が一筋横に流れた。
「あら・・・・アンジェ、空を見ててごらん。いいものが見られるよ!」
急に足を止めて、子供のような無邪気な表情で、空を見上げたオリヴィエが言った。
「いいもの?」
何のことだかわからずに、でもとにかくアンジェは慌てて空を見上げた。
「わ・・・・・・あ・・っ」
アンジェリークは、その眼前に広がるものを見て、絶句した。空いっぱいに広がるそれは有無を言わさないパワーで、彼女を圧倒した。横にいるオリヴィエも空を凝視していた。彼もまた、久々に見るそれに、心を奪われていたのだった。
「・・・・オーロラ・・・・・!私、初めてです、オリヴィエ様。なんて綺麗・・・・」
しばらくたって、やっとの思いで口にした言葉。アンジェリークにとって、精いっぱいだった。
オリヴィエは、優しい微笑みを湛えながらアンジェリークに向き直った。極寒の夜、恐ろしいくらいに冴え渡った空気の中、彼女だけがオーロラの光を受けて薄く発光している。
「こんな辺境の星にでも来なければ、見られないシロモノ。まさかこんなタイミング良く見られるなんてね・・・さすがにこればかりは聖地でも見られないからね」
言い終わって、オリヴィエはまた空に視線を上げた。アンジェリークは何も言わなかった。オリヴィエも返事が欲しい訳ではなかった。それから後は、ふたりただただ空を見つめ立ち尽くしていた。そんなふたりの姿はまわりの凍てつく木々と少しも変わらないように見えた。
空に広がるオーロラは、さまざまな色を湛えながら、まるで軽やかなダンサーの足取りで、くるくると空に踊った。少しも一定の形にとどまっていることはなかった。あるところでは激しく渦を巻き、あるところではゆるやかに漆黒の空に光を伸ばしていく。青白くもあり、鮮やかな緑や黄、紫などの色の部分もある。もう一口に何色とは言えず、絶えずいろいろな色が混じり合い、反発しあい、あらわれては消えていくのだった。そして形がなし崩しになり・・・・薄い雲と同じように風にたなびいて、光の饗宴は終わった。
どのくらいの時間が経ったのか、アンジェリークにはわからなかった。数時間程も呆けて立ち尽くしていたようにも思うし、ほんの一瞬の出来事のようにも思えた。ただ、さっきまでの光の渦と帯は、その跡形など何も残さずに今は消えている。
(オリヴィエ様の見せた一時の夢だったのかしら・・・・)
アンジェリークには、そんな風にさえ思えてきた。
「アンジェ、このままで行く?」
気が付くと、オリヴィエがいつもの少し悪戯っぽい笑顔で、囁いた。
「えっ?このまま?」
「私はぜんぜんかまわないわよ〜」
といってオリヴィエの手のひらに力がこもった。そう、いつのまにかアンジェは、オリヴィエの手を握りしめていたのだった。
「えっ?あ?あたしったら・・・・!すみません、オリヴィエ様!」
電気にはじかれたように、手を離す。それと同時に、まるで火を入れたストープのように、アンジェリークの顔がみるみる紅潮した。
「あっはは、あんたってホントに面白いねぇ。・・・さ、行こうか、体もいい加減冷え切ってる」
アンジェリークの様子を、これ以上もない穏やかな眼差しでみつめながら、オリヴィエは何か自分が柔らかく優しい気持ちで満たされていくのを感じていた。
(この故郷の土の上で、そんな気持ちに満たされることがあるなんて、思ってもみなかったよ、アンジェリーク・・・)
|
HOME
|
NOVELS TOP |