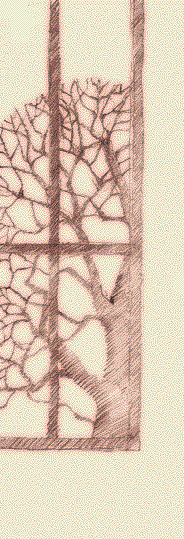

アンジェリークは寝付けなかった。昼間の衝撃的な出来事は、昨日までの呑気な気分を一変させてしまった。黒い森、アヌーシュカの運命、オリヴィエの表情・・・・。いろいろなことが頭をめぐる。しかし、感傷的になっている場合ではない。ことは現実なのだ。
「・・・・ふぅっ・・・・・・」
アンジェリークは、やおらベッドから起きあがると、サイドチェストにあるガウンを取り出し、はおりながらドアに向かった。時計を見ると、既に午前一時を回っている。
「仮にも女王候補がふらふら出歩く時間じゃないわね。・・・でも眠れない時はあれに限るんだもの!」
アンジェリークはティーラウンジに向かった。勿論、こんな時間では営業時間は終了している。しかし、場所自体は解放されている。
(さすがにこの時間だと誰もいないわね)
アンジェリークは照明のスイッチを入れようと壁をさぐったが、指に確かに触れたスイッチはなんの反応も示さなかった。電源が既に落とされているらしい。しかし、照明がなくとも、広いラウンジは仄かに明るかった。向かい側の壁一面が、広く外に向けてガラス張りになっているので、ラウンジは氷雪に反射した星の明かりで、ぼうと青白く光っていたのだった。
(明かりなんか付けない方がよっぽどきれい・・・。このままでもかまわないか)
アンジェリークはぐるりラウンジを見渡した。
一瞬、息が止まるかと思った。
(誰かいるっ!)
入口から死角になる一番はじの席に、誰か一人、座って外を眺めている。幸いにも、こちらには気付いていない様子だ。
(こ、こんな夜中に出歩いてるところを見つかったら、聖地に報告されちゃって、ジュリアス様かなんかに呼び出しくらっちゃって、自覚がなってないとか言われちゃって、監督不行届だ!なんてことになっちゃってオリヴィエ様にまで迷惑がかかっちゃうっ!)
すぐさま部屋に戻らなければ、見つからないうちに。
と、宵闇にも目が慣れてきた彼女は、その人物が誰であるかを知った。
(オリヴィエ様だわ・・・・・)
しかし、その様子はいつものオリヴィエからは想像もつかなかった。いつも微笑みの絶えないその表情は、暗く冷たくこわばり、外の氷原を凝視している。とても気軽に声をかけられる雰囲気ではない。オリヴィエ自体がまるで氷の彫刻のように見えた。
アンジェリークは、くるり、と踵を返した。見てはいけないものを見たような気がした。ここは部屋に帰った方が良さそう・・・・、と思った矢先。ガウンの裾がラウンジの椅子にひっかかり、予想以上に容赦なく大きな音を響かせた!
「誰?」
「あっ、はい、あのっ!別に、あの、すぐ帰るつもりで・・・・」
「・・・・・アンジェか。どうしたの、こんな夜更けに。眠れないの?」
「あ、はい。ホットミルクでも飲んだら、落ちついて眠れるかなーっと思って。オリヴィエ様がいらっしゃるなんて思ってもみなくて。すみません、お邪魔して」
「邪魔じゃないよ、別に。私も少し眠れなくてね。こっちにいらっしゃいよ、一緒に飲もう」
湯気の立つミルクが注がれた大ぶりのマグカップを携えて、アンジェリークはおずおずとオリヴィエの隣に座った。何だかいつものオリヴィエと違って、今夜のオリヴィエは近寄り難かった。なにか取り巻く空気の色が違うような気がした。星明かり、氷原の反射の青白い光に照らされているからなのかしら?
「・・・オリヴィエ様・・・お酒・・?」
オリヴィエの手にあるのは、確かに琥珀色をした液体で、グラスのそこで揺れていた。
「ああ、そう。たまには・・・ね。部屋で飲むよりここのがいいかと思って。・・故郷だとハメを外したくなるのかな」
酔っているのだろうか、ほんの少し自嘲するようなニュアンスが、込められているような気がした。こんな彼をアンジェリークは知らない。
オリヴィエは、また外の景色に目をやった。アンジェも一緒の方向を見据えたが、そこにはどこまでも続く氷の原野以外は何も見えなかった。ブルーグレイ一色の景色。木の一本すらも無い。
星明かりは何の影も作ることなく、鏡のような氷原に光を溶かしこんでいる。単色の、美しい景色ではあるけれど。
そしてオリヴィエは、静かに話し始めた。
「ねえ、アンジェ。何にもないでしょう、この星。私はこんな星で、二十歳になるまで過ごしたんだ。一年中こんな天気で、昼も夜もそう変わらない。吹雪でなけりゃ良い天気ってね。小さい時から、この星を出ることばっかり考えてた。イヤでイヤで仕方がなかったわ。この星をとりまく無気力な感じも、なにもかもが嫌いだった。いつかどうにかして出てってやるって心に決めてたの」
オリヴィエは少しもアンジェの方には向き直らずに、氷原を見つめながら、ブランデーグラスを呷った。アンジェリークは、ただそんなオリヴィエを見つめることしかできなかった。彼は話続けた。
「十七のとき、さあ出てってやるぞって、自分なりに計画を立ててさ。取りあえず、隣の星にさえ行ければ、この星からさえ出られれば何とかなるって思って。ぎりぎり片道の旅費だけ、頑張って貯めたのさ。でも計画も大詰めってとこで、聖地から使いが来た」
「女王陛下の・・・・」
「そう。私に次なる『夢』のサクリアが授けられたので交代の時期を待て、ってね。普通、守護聖になる資質を持つものは、早くから養成機関に召し上げられてしかるべき教育をうけ、そこから交代って話になるんだけど、私の場合、こんなへんぴな星にいたせいか、見つけられるのが遅かったらしいのよね。そんな話、いきなり聞かされて家族も私もびっくり仰天さ」
淡々と語り続けるオリヴィエ。ほとんど表情は変わらない。飛空都市で見る彼はいつでも笑っていて、周囲まで明るい気分になるような優しさに満ちていて、どんなに落ち込んだ時でも、オリヴィエの励ましひとつで立ち直るなんてことはアンジェリークにとってよくあることだった。でも。今夜のオリヴィエは何か見えないものに向かって、憎々しげな表情さえ見せる。お酒のせいなんだろうか。
心配そうな瞳でオリヴィエの横顔を見つめる少女のことなど、いないもののように、オリヴィエは話し続けた。
「守護聖を輩出するってのは、その家にとって非常に名誉なことでね。そうあることじゃないし。過去一回でも輩出した血筋なら、名家として子々孫々まで語り継がれちゃう訳。ジュリアスん家みたいに、もともと家柄がよくって何人も守護聖を輩出してて、そういうのに慣れてる家ってのもあるんだけど、うちは単なる庶民階級。もうね、青天の霹靂よ、そんなこと。しかも急に言われたもんだからねえ。会ったこともないような親戚が、どこからか聞きつけてしょっちゅう家に来るようになった。みーんな魑魅魍魎みたいな奴等よ。聖地から支給される多額の支度金のおこぼれに預かろうって算段。で、さんざおだてて好き勝手飲み食いした後にこういうのよ、『夢の守護聖って何の力があるの?美を司る?へーえ・・』ってね。まるで役に立たない力だって顔に書いてあるの!おっかしいったらありゃしない」
誰もいないラウンジにオリヴィエの乾いた笑い声が響いた。その声は行き場なく、数度エコーを繰り返して、寂しく消えた。もちろんアンジェリークは笑わなかった。笑えなかった。ただ身を堅くして、マグカップに添えた両手を見つめていることしかできなかった。
オリヴィエはグラスに残ったブランデーを一気に飲み干すと、ボトルに手をかけ、手荒に継ぎ足した。勢いがつきすぎて、ブランデーはグラスの淵をすべり少しこぼれた。
「そんな生活がどんどん家族も変えてった。お人良しで優しかった父も、機転が利いて働き者だった母も、みんなお金でおかしくなっちゃった。しまいにゃ、なんでそんな大金が家にあるようになったのかさえ忘れちゃったみたいに、みっともない贅沢に呆けてた。私が引き替えなんだってこと、忘れてた・・・・」
「オリヴィエ様!」
アンジェリークは大声を出して机に手をつき立ち上がった。これ以上、聞いていてはいけない。
そして、彼女は持っていたマグカップの中身、まだ十分に熱を保ったミルクを一気にオリヴィエの持つブランデーグラスにあけた。
面食らうオリヴィエ。
「アンジェ・・・っ・何を・・・・」
見上げると、彼女のその瞳には大粒の涙が後から後から溢れて、頬を伝っては落ちていた。
「アンジェリーク・・・・・」
「お、オリヴィエ様っ、ブランデー入りのホットミルクは催眠作用があるって聞いたことあるし、それ飲んで早く寝たほうがいいと思いますっ!私も、もうさすがに眠いしっ、明日にも差し支えるし、部屋に戻ります!おやすみなさい!」
アンジェリークは深夜にふさわしくない大声で、一気に喋るとオリヴィエの顔も見ずに走り去った。ガウンの裾がひらり翻り、足取りを追った。
オリヴィエは呆気にとられるのと同時に、我に返ったように言った。
「私は・・・いったいあの子相手に何をくだらないことを・・・・・」
手にしたグラスはうってかわって暖かく熱を持ち、オリヴィエは再び血が通いだしたような錯覚を覚えた。
そうして、彼女オススメの『ブランデー入りホットミルク』を、一気に飲み干した。
「・・・・・おまけに、砂糖入ってるじゃないか、これ・・・・」
オリヴィエは少し微笑んだ。
(ああああああっ、ますます眠れないじゃないの〜)
アンジェリークは暗闇のなか、何度も寝返りを打っては悶絶していた。
(オリヴィエ様のあんな話聞いちゃって、しかも最後には話の途中でグラスにミルクぶち込んで逃げてくるなんて〜、私ってサイテー・・・・私がもっと気の利いた事言えたなら、良かったのに・・・・・)
アンジェリークは今日ほど自分のふがいなさを悔やんだ事はなかった。もちろん、今までだってそういう事はあったが(しかも何度も)今回ほどではない。
「いつもいつも私が落ち込んでる時には、元気になる言葉をかけてくれるオリヴィエ様なのに。私は何も返せない・・・・」
そんなことを想うと、せつなくなって、また涙がこぼれてくるのだった。
(明日、どんな顔して会えばいいの・・・。こんなことなら飛空都市で寮の部屋の掃除でもしてたほうが良かったよー・・)
|
HOME
|
NOVELS TOP |