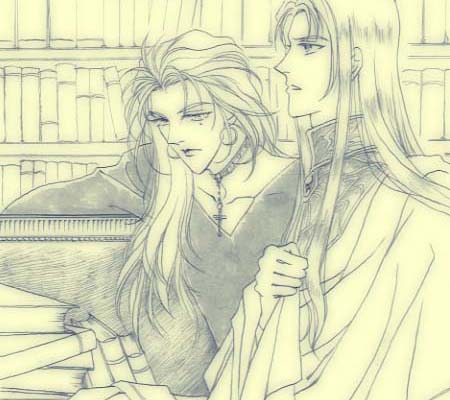オスカーは、あの時と同じ広間に通され、あの時と同じ場所に腰を下ろしていた。
分院から馬を駆った彼の、行く先はひとつしかなかった。王となったアディールの住まう、この城。約束を忘れた訳ではない。しかし、あのまま帰って何になる?自分は何のためにわざわざこの星に来たのか。この星の詳細を確認しに来たわけではない、そんなことならもう既に用は済んでいる。・・・この胸騒ぎ。未だはっきりとは正体を表さぬそれが何なのか確かめに来たのだ。守護聖としてではない、自分個人として。
それにはアディールに会わねばならない。そう思った。そして彼は今こうしてここに座っている。
待たされている間、オスカーは周囲を眺めているしかすることがなかった。
あの日のことが思い返される。あの日、この広間には様々なものが溢れかえっていた。祭りを祝う人々、治める各国から贈られ山のように積み上げられた品々、美味なる珍味、貴重な酒、華やかな女達、美しい音楽。あらゆるものがこの星の繁栄と王への賛美を指し示していた。
広間だけではない、その先にあるバルコニーに出て見おろせば、そこには幾万の民が歓喜に包まれ、口々にこの国に生を受けた喜びを語り合っていた。その人々の躍動が城の壁を伝って楽の音の律動と重なって。この星全体が自らの栄華を誇っているようなイメージさえ湧いた。
それがどうだ。今のこの閑散とした寒々しい空気は。今のこの場所には少しの色も熱もない。宴の人々がいないだけで、他のものは同じなのに、まるで別の場所だ。いや、同じなだけに、「違う」という印象を抱くことに強い違和感があった。
彼の視線の先にあるバルコニーからのぞく空は、厚い雲がたれこめていた。
「女王陛下アディール様のおなりでございます」
オスカーの思索を破る声。振り返るとそこには、華美ではないが一星の主らしくきちんと装った女が頭を垂れている。その頭上にはいつの日か見た剛健な王の頭にあったものと同じ、黄金の冠が鈍く光っていた。
ゆっくりと、その王冠の下から顔がのぞく。
「お久しぶりでございます、オスカー様」
オスカーはすぐに返事ができなかった。
この星の、過ぎ去った時間が彼女にとってどのようなものだったのか、その姿が一番物語っていたからだった。
顔は青く肌艶は失われ、見るからに疲れはて痩せた一人の女の姿。
自分を真っ直ぐ見つめる緑の瞳、長い銀の髪。唯一面影を残すそれが無ければ、記憶の中の彼女とは少しも重ならない。この星のすべてのものから愛を受けて、暖かな日溜まりのような輝きを放っていた幼い姫。15年経ったとはいえ、こうまで変わるか。
ただそれでも・・彼女は美しかった。磨き上げられた細い刃の切っ先のように、極寒の中月光を浴びて光る鋭くとがった氷柱のように。それは王者の持つ威厳とはまた違って、何か悲壮な近寄りがたさを放って見えた。
「これは・・・見違えた・・・」
やっとの思いで発せられた声に、アディールは小さく微笑んだ。
「オスカー様は何一つお変わりなく。初めてお会いした日が戻ってきたようですわ」
彼女はゆっくりとオスカーの正面下座に据えられた椅子に向かって歩みだし、座った。
「なぜ、そんなに遠く離れて座るんだ?」
「物を知らなかった昔とは違いますわ。私ももう二十を越えて、この星の主ともなりました。身の程はわきまえております」
「みずくさいことを言うじゃないか。俺はかまわない・・・もっと近くで顔を見せてくれ」
過ぎてしまった時間、変わったのはその姿だけだと確認したい。自分の知っている彼女だと、思いたい。焦りにも似た気持ちだった。
「そんな、畏れ多いことでございます。私はここで」
アディールは目を伏せそう言った。頑ななその声色に、オスカーはそれ以上強くは言えなくなる。
「・・・いらしていたなど、思いも致しませんでした」
それをあまり喜んでいないのは表情からも声からも明らかだった。招かれざる客という肩書きが、その一言でオスカーに与えられた。彼はそれでも心持ち明るい声で言った。
「深い意味は無いんだ、ただ・・懐かしくなって立ち寄ったまでで・・」
「ふふっ、相変わらず子供みたいな言い訳をなさる」
浮かんだ笑みはすぐ消える。
「オスカー様にとって、懐かしむほど時は経っていないはず」
「・・・・・・・」
「なぜこんな急にいらしたのか、理由を聞かずともわかります。この星の惨状・・・もうお聞き及びなのでしょう?」
黙り込むオスカーから視線を外し、彼女はバルコニーの方向に歩んだ。
「あれから15年が経ちました。父が急逝し、私が後を継いで。・・・途端に太陽が暗い雲に覆われたかのように、この星は翳りだし。私がどんな手を尽くしても状況は悪化するばかり。若すぎる、女の王など・・いいえ、私など役にも立たないと、星からあざ笑われているかのよう」
「・・・言わなくていい」
「言わせて下さいませ。自らの口で言うその方がどれだけ気が楽か」
自分が王になったら父を越える名君になってみせると、輝く眼差しで未来を語っていた少女。誇りも理想も高い分、それにそぐわぬ今の状況がどれだけ彼女を痛めつけているか、オスカーにも理解できる。
「・・・・どんな星にもこういった時期はある。父王に比べて能力が劣るということではないだろう」
「お気遣いは結構です。実際のところ、劣っていようがいまいが、今は私がこの星の王。私が導いて行かねばならない。必要でないとなれば民が容赦なく私の胸を貫く矢を放つまで。それだけの話ですわ」
同じ意味のことを、彼はついさっき別の場所で口にした。王に求められるは政治能力だけではないと。なのに今、自分は諭されるようにその言葉を聞かされている。
甘っちょろいセンチメンタリズム。安っぽい同情。オリヴィエとリュミエールが言うように、そんなことが理由で自分はここまで来たのか。そうではないと他の者になら胸を張って言えることが、なぜ本人には言えないのか。
「女王陛下のご裁可はどのようなものなのですか」
「え?・・・あ。ああ」
オスカーは思わず口ごもる。そんなものは無い。ここへ来たのは勝手な思いこみなのだから。何かできることがあるかもしれないと思った自分が傲慢に思えた。自分個人として、などと言いつつ結局は守護聖の立場を振りかざす結果になって。思えば当然だ。個人、などというものはもうきっと自分にはないのだ。あると言い張ったところで、誰もそう受け取る者がいないのでは、結果無いも同じだ。
「・・・・できればこういう事態は避けたかった・・・。ですが、自らの無能を呪うしかありませんわね。この星は私の支配下にあっても、宇宙は聖地のもの」
そう言って彼女は肩を落とす。この星の苦境よりも、今自分がここにいることの方がアディールに、この星の王にとって苦痛であることを、オスカーは思い知らされる。
「すまない、本当に立ち寄っただけなんだ。陛下の裁可など無い。この星は・・」
言い終わらぬうちに彼女は顔を上げた。見開かれた瞳から、強い眼差しがまっすぐにオスカーに注がれる。
「・・・では・・・オスカー様はわざわざ今のこの星、今の私の姿を取り立てて理由もなく見にいらしたというのですか」
「そういうことに・・・なってしまうな」
「・・・それは随分と・・・」
アディールは小さく笑い声を洩らした。
「楽しげな退屈しのぎですわね」
痛烈な皮肉。
「滑稽でしょう、子供の夢語りとは言え、立派な理想論を振りかざしていた私をご存知なのですから。穴にでも入りたいとはこのこと」
「そんなことはひとつも思っていない・・・!」
オスカーは声を大にした。勢い、腰を浮かせる。
「では、何を思ってわざわざいらしたというのです。守護聖様がそうおいそれと聖地をお出にならないことは知っています。つまらない同情ならいりません、はっきりとおっしゃってくださって結構です」
オスカーは言葉が継げず、腰を再び椅子に戻した。敢えてここで何かを言っても意味は為さないだろう。黙り込むオスカーに、彼女は呟くように、しかしきっぱりと言った。
「おっしゃることが無いのなら、・・・これでお引きとりくださいませ」
彼女によって導き出された答は、それ以外無い見事な正解にオスカーにも思えた。そして間違った式を立てていたのは自分だけなのだ。リュミエールにもオリヴィエにも最初からそれはわかっていた事だ。
無言のまま、オスカーは立ち上がる。最後にと、彼女の方を見た。
彼女の言った通りになった。最初のプレゼントは、この目の前のレディから今まさに捧げられようとしている。
瞬間、彼女の背後が光った。直後とどろく雷鳴。間をおかずにそれは豪雨を連れてくる。バルコニーから強く風が吹き込み、二人の髪を煽った。外は既に嵐だった。
「なんということでしょう・・・よくあることとは言え・・・」
異常気象。書類の文字が思い起こされた。
「これでは・・・今は外には出られませんわ」
急の足止め。複雑な思いのオスカーに反し、アディールは冷静だった。彼女の横顔からその真意を知ることはできない。今のことだけではない、再会してからこっち、彼女は生の感情を一度も見せていない。鉄壁の防御。そうまでの態度が逆に気になった。
「待っていればすぐおさまるかと。オスカー様、ここは風雨を避けるものは何もありませんわ。奥へまいりましょう」
相変わらずの無表情で、彼女はオスカーを促した。
地の守護聖は、ドアの開く音に書物から顔を上げた。
「ああ、お呼び立てしてすみません、オリヴィエ、リュミエール」
「別にかまわないよ、ルヴァ。何事?」
「先程、王立研究院から私に報告があったのですが」
オリヴィエは勝手知ったるとばかりに、まっすぐ部屋の奥に歩き出す。ルヴァの私室に招かれた客の最初にすることは決まっていた。自分の座るべきソファに本来の仕事をさせること。ルヴァとリュミエールも作業に参加する。分厚い本の山をかき分け横に積み上げながら、オリヴィエは言った。
「あ・・・ああ、もしかしてオスカーのこと?」
「やはり・・・あなた方はご存知だったのですね」
ルヴァは小さく息をついた。
「ルベリという惑星から聖地への報告で・・・私もいったいどうしたものかと」
「どうしたものか、と言いますと?オスカーが何か?」
リュミエールの声は不安げだ。
「何も聞いてはいないのですか?」
逆に問い返す地の守護聖。オリヴィエはやっと確保できた自分の場所にどっかりと腰を下ろして、敢えて明るい声で言った。
「ワタシたちが知ってるのは、ヤツがルベリに行ったことだけ。アイツが聖地抜け出すなんざ別に珍しいことでもないし、そんなことに今更目くじら立てるのジュリアスくらいでしょ?すぐ戻ってくるって言ってたし」
「そう安心できたものでもないようですよ、オリヴィエ」
側仕えの者に茶の支度を言付けてから、ルヴァは曇った顔を二人に向けた。
「ルベリの分院を出たきり、戻らないそうです。以後連絡もないと」
「え・・・?」
オリヴィエとリュミエールは同時に声を上げた。ルヴァは続ける。
「何か事故にでも巻き込まれたのではと、あちらでは大騒ぎで。しかし私としてもオスカーがそんな場所にいることすら寝耳に水の話・・・」
オスカーが分院を出て行くところなどひとつしかない。二人にはそれがわかっていた。
「・・・あんっの、馬鹿!」
「は?・・オリヴィエ、やはり何か知って・・」
「あ、何でもありません、ルヴァ様」
慌ててリュミエールが打ち消す。
「オスカーのことです、物見遊山で外に出て、もしかして道にでも迷ったのでは・・・」
「そ、そうよーお、アイツだったら事故よりそっちのがまだリアリティあるよ。殺しても死なないような体自慢だもん」
運ばれて来たティーカップを目の前の二人に勧めつつ、ルヴァは言った。
「一応サクリアの状態に変化が無いので、無事は知れているんですけれどね。でも、このあいだ行ったばかりの惑星ですし、道に迷っているとするのもどうかと思いますがねー」
口調は穏やかであるが、二人の言い分はあっさりと否定している。そう簡単に言い逃れることができるほど、この地の守護聖は単純でなかった。彼はにっこりと笑った。
「推測でもかまいません。つつみ隠さず言ってください、あなた方の胸の内にあることをね」
先輩守護聖の笑顔に降参し、オリヴィエは背もたれに体を預けて肩をすくめた。
「あーあ、やっぱルヴァは騙せないか。抜けてるように見えて、ポイントは外さないんだよねえ」
隣のリュミエールが同意する。
「仕方ありません、オリヴィエ。もしも本当に事の大事に至ってからでは遅いのですから・・・」
「まあね。そりゃそーだ。・・・ルヴァ、アイツは多分、ルベリの王宮にいるよ。長々戻って来ないのは、間違いない、オンナにひっかかってるからだ」
「女?」
オリヴィエとリュミエールは事の次第をルヴァに口々に語った。
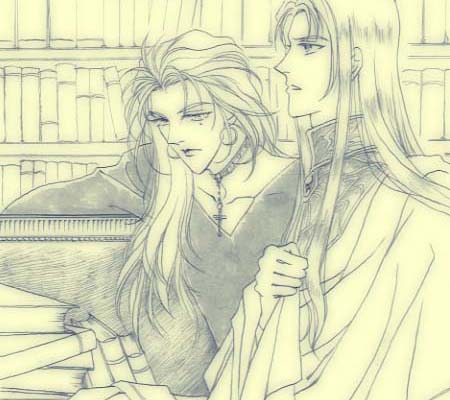
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |