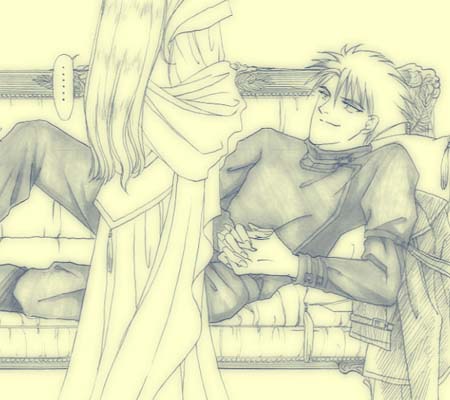相変わらず、とりたてて変化のない日常が過ぎた。オスカーは今日一日の仕事を終え、王立研究院のフロアのソファに腰を下ろした。誰もいないことに気を許して、すぐにソファの上に足を投げ出す。
「お・・と、なんだリュミエールか」
扉に見えた人影が誰であるか知って、態度悪く寝そべったまま、オスカーは言った。
「随分なご歓迎ですね」
あからさまに不快な表情で、リュミエールは彼を見る。彼でなくてもこんな挨拶には気を害するだろう。
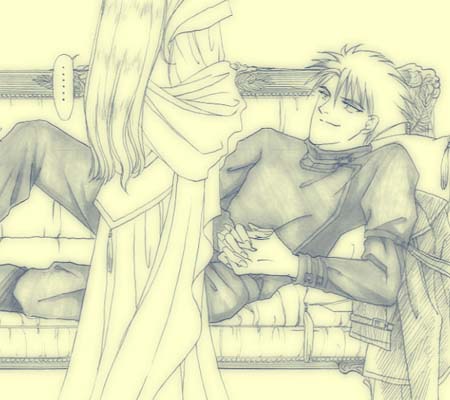
「すまん、つい。オリヴィエ待ってたもんでな」
「このようなところで?」
「ああ、もうすぐここへ来る予定だというんで、ついでに」
「待ち伏せていると」
「待ち合わせ、って言えないのか?」
「申し訳ありません、つい」
リュミエールも切り返す。この二人の会話は一事が万事この調子だ。
「時間潰しのお相手をしている暇は、私の方には残念ながらありませんので」
「別に頼んでないさ。誰かさんみたいにくだらんうわさ話する茶飲み相手などいなくても俺は一人で時間くらい潰せる」
「夜遊びのお相手は必要でも?」
「・・・察しがいいな。ここんとこ聖地から出てないからな、今晩あたりどうかと」
「このあいだ公務に行ってきたばかりではないですか」
「あれは仕事だ、数には入れん」
「・・・まったく」
リュミエールはそれ以上言葉を継ぐのをやめ、奥の扉から現れた研究員から書類を受け取った。そこに彼が今から水のサクリアを送るべき惑星のデータが記されている。
「・・・」
「どうした?」
一瞬曇った水の守護聖の顔にめざとく気付くオスカーに、リュミエールは書類から目を離さずに答える。
「この惑星・・・ルベリ・・・私どもが先頃行った、あの星です」
「それがどうかしたか?」
「どうということはないのですが・・・。統治者が代わったのですね。それにともなって、惑星の状態もいささか不安定の様子」
「・・・・見せろ」
言い終わらないうちに、オスカーはリュミエールの手から書類をひったくっていた。リュミエールも横から一緒に書類をのぞき込む。
「異常気象による不作続き・・・内乱の兆し・・・。なるほど、自ずと上がってしまったあなたのサクリアを、私の水の力でバランスをとろうということなのですね」
ルベリは閉じられた自星で自給自足の生活を営む昔ながらの星だった。異星間貿易などにも前向きでない。知的レベルが遅れているというより、ルベリには「必要がない」からだった。さほど大きな星ではない。その規模には十分すぎるほどの収穫が自星で得られ、民はそれで満足していた。そんな星が数年にも及ぶ不作に見舞われるのは、大打撃のはずだった。民の不満も募ろう。実際、書類上のデータにもそういった意味が見てとれた。
「私たちがルベリの豊かで美しい風景の中にいたのはつい先日のことなのに・・・。本当に星は生きている。私のサクリアで、荒んだ星が癒されてくれるといいのですが」
豊かで美しい・・・この聖地にも似た、星。まるで嵐の予兆のような黒雲が、あの広い平原の空に湧きたっていくイメージが、オスカーの脳裏に浮かんだ。そして共に思い起こされる、あの無邪気な緑の瞳。
「・・・・王が代わった、と言ったな」
アディールが後を継いだのだろうか。
「そのようです、ほらここに」
リュミエールの指し示した先には、まさしく彼女の名が記されていた。
何かにつき動かされるように彼は立ち上がった。身体は無意識に研究院の奥へと向いていた。彼の背中に、鋭い声が飛んだ。
「オスカー、どこへ行くんです」
リュミエールは、勘が良い。
「・・・わからんお前じゃないだろう」
「自分が何を言っているかわかっているのですか。そんな勝手が許されるとでも?」
「・・・元々今夜はどこかへ足を伸ばそうと思っていた。その行く先が決まっただけだ」
心のざわめきを押し隠し、取るに足らないことだと言わんばかりに、オスカーは笑みさえも浮かべて言った。しかしリュミエールの表情は変わらない。
「他の場所なら見逃す気持ちにもなる、でも、ルベリは駄目です」
「おかしなことを言うな、リュミエール。他がよくて何でルベリは駄目なんだ?察しがよすぎて、気の回しすぎだ。別に何をするでもないさ。ただ・・・興味を持っただけだ」
「守護聖が一惑星に殊更の興味を持つは厳禁なことのはず」
リュミエールは声を抑えて、静かに言った。
「このような微妙な状態の星に、我等守護聖が直接赴くなど、どのような影響を及ぼすか・・・。切羽詰まっているのならそれも仕方ない。しかしこの程度の星は、いえ、これより酷い状況の惑星は他にいくらでもある。ルベリは、予断を許さない状況ではあっても、あなたが行かねばならないという必要性はまったくありません」
リュミエールの言うことはいちいちもっともだった。正論すぎる正論。しかし言われて、はいそうですかと納得するオスカーではなかった。リュミエールは畳み掛けるように続ける。
「あなたとあの姫君は随分と親しくしていた・・・心配する気持ちもわかります。でもオスカー、悪戯に触れてはいけないものもあるのです」
「・・・・・・・・・」
なぜかすぐには答えられなかった。言い負かされている場合ではないと、彼の声は一段と大きくなる。
「俺があのお嬢ちゃんに同情して星に何か手を下すとでも言うのか?くだらん、お前の言ってることは取り越し苦労だ。なんと言われようと行くぜ、俺は」
「少しは人の話を・・・・!!!」
「こんなとこでケンカ?おっきい声がするから何かと思えば」
「オリヴィエ、良いところに!」
新たに場に加わった登場人物に、思わず同じ言葉が二人から同時に洩れる。
「・・なあに、それ」
オリヴィエは尋常でない雰囲気の二人の顔を眺めた。どうやらいつもの口げんか程度の話ではないらしいことを、察したようだった。会話の内容をざっと聞く。
「・・・ふーん。アンタタチがこないだ行った星がねえ」
「オリヴィエからも止めてください」
「リュミエールは大袈裟なんだ。ただ行くだけって言ってるだろう?」
「はいはい、言い分はわかったから、怒鳴るのやめてよね。耳が痛くなっちゃう」
オリヴィエはしばし考え込む風にして、まずはオスカーのほうを向いた。
「ワタシが賛成するのは、リュミちゃんのほう。アンタは行くべきじゃないと、私も思うね」
「オリヴィエ・・俺は」
「どう言い訳しようと、話の正当性がどっちにあるかなんてアンタにだってわかるだろ」
「・・・・」
「でも。それでも、どーーしてもって言うなら、行けばいい」
「オリヴィエ!それでは・・・」
「リュミちゃん。こいつが言い出したら聞かないヤツだって知ってるでしょ?ここで無理にうんと言わせたって、どうせ行くに決まってる。今度は誰にも黙ってね。そっちのがよけい面倒事になりかねないよ」
「それはそうですが・・・」
「ここは一発恩でも着せといた方がよっぽど効果的だよ」
オリヴィエの言うことに納得しながらも、まだ何か言いたげなリュミエールだった。彼を説得するようにその肩をぽんとひとつ叩いて微笑んでから、オリヴィエはオスカーに少々強い語調で言った。
「でも、たとえバレてもフォローはしないよ。共犯になるのはまっぴらゴメン。私らに迷惑かけないよーにしてね」
「悪いな、オリヴィエ、リュミエール!感謝する」
「殊勝なこと言うんじゃないよ、キモチワルイ。あ、でも条件付けておこうか」
「条件?」
「くだんの姫君・・・今は女王様か、には会わないこと」
オリヴィエも結局はリュミエールと同じことを考えているようだ。
「・・・おいおい、甘っちょろいセンチメンタリズムは俺がもっとも嫌う感情なんだぜ?少しは俺を信用してくれ」
「信用なんて言葉、一番アンタから遠いところにあるよ、ことオンナ関係はね!別に何するつもりもないって言ったのはアンタだ。難しい条件でも無いでしょ。ほらほらあ、バレないうちに行って帰って来れば問題ないんだから、とっとと行っといでっ!」
「すまん」
オスカーは寸刻を惜しむように踵を返し、二人を後にした。
王立研究院の分院は、大抵星の中央とは少し離れたところにひっそりと設置されている。あくまで聖地のための設備であって、惑星の政治とは一線を画し、互いの干渉は必要最低限に留めようとする配慮だった。
急の守護聖の来訪に、場は緊張していた。何か自分らの仕事に不備でもあったのかと言葉無く伺っている。オスカーは彼らに責任はないことを軽く説明しただけで、後は差し出された書類を一心に読んでいた。
同じだった。ルベリに実際来たと言って、新たに得られることは既に無い。ここでの調査結果を聖地は汲み上げているのだから当然だ。
オスカーは溜息をついて窓の外を見やった。以前来たときと一見してはなんら変わりないようにも見える。同じ場所に同じ木が立ち、同じ森があり、同じ山が聳えている。そのすべての、印象がどこか違う。そう・・・まるで変色した古い写真を見るような。
「あの祭は・・・この星の時間でどれくらい前になる?」
「オスカー様とリュミエール様がいらしたあの大祭のことですか?」
一番側近くに控えていた者が答える。
「15年前になります」
「15年・・・・」
では、アディールはもう、自分と同じ年頃に成長しているのか。
勿論、オスカーとて8つの子供が即位したなどと思っていたわけではない。時間の流れが違うことなど、百も承知だ。しかし、それを実感するに、自分の脳裏に浮かぶ少女の姿はあまりに記憶に新しすぎた。
「・・・あの・・・それで、この惑星は何か危機的状況を迎えているのでしょうか?聖地の干渉が今から必要なほどに・・・」
この分院の長らしい男が、おそるおそるオスカーに問いかけた。
「あ、いや、そんなことはない。そう安心できたものでもないが、この程度ならば陛下は星の自力で沙汰するべきと判断なさるだろう」
オスカーの言葉に安心したのか、分院の長は急に饒舌に炎の守護聖に話しかけ出した。彼らにとっても直接守護聖と話すなど滅多にない栄誉である。
「実際、もっと酷い状況もあり得ました。私見ではありますが、この星の統治者はよくやっていると思います。・・いかんせん、この星は今までが豊かすぎた・・・民はあまりに長かった幸福の時代を普通のことと未だ思っているのです。いかに手を施しても、過去と同じレベルにならなければ彼らは満足しない。その不満が解消されない以上、上向きになるものもならないという悪循環で」
この星の統治者。苦境に立たされた、美しく聡明な女王。オスカーのイメージには顔が無かった。
「・・・そうは言っても、民草の心を纏めるのも王の仕事だ。有能であっても人望が無いのでは片手落ちだ」
人はどこまでもどん欲だ。最悪の事態を免れたことを喜ぶよりも、最高の幸福が手に入らないことを強く不満に思う。仕方のないことだ。王たるもの、その理不尽に耐え、越えねばならない。そこに同情したところで何の意味もなかった。
「さすが強さを司る御方らしいお言葉でございますね。・・・ごもっともでございます」
目の前の男は小さく笑ってから、ただ、と続けた。
「ちょうど今の王が即位したのと相まって、状況が悪化したこともあって。天候など人の自由になるものではないのに、民はまるで新王が悪魔を引き連れて来たのだと言わんばかり。若い女の王だというのも人々の不興をかう原因で。多くあった反対を押し切って自ら即位の意志を貫いたということですが、いささか気の毒です」
「反対?確かこの星の先王には王位継承者はひとりしかいなかったはずだ」
アディールは王の一粒種だと聞いていた。反対もなにも、彼女しかいないではないか。
「その通りです。しかし先王は後を継がせたくなかったようですね、王になればいろいろと辛いこともある。そんな立場に愛娘をおきたくなかったのかもしれません。早くから婿を取るのに熱心で。でも適当な者がいなかったのか、今度は王女の子に継がせようと、あっと言う間に親ほども歳の違う配下の領主に嫁がせてしまった。その途端、先王は急逝したのです。運命の神は随分と王女を翻弄なさる・・・」
15年。決して短くはないその時間。聖地で眺める書類の一行の裏に、これだけの事実がある。チェスのコマでも動かすようにその動向を操れる立場にいて、知ることの出来ない星の真実、民の心。数多ある宇宙の星のひとつひとつに、そのような細かいケアは不可能だとはわかっていても、聞けばやはり思うところあった。
彼女はどうしているだろう。
「思えば即位が、先王の決めたことではない初めての自身の決断だったのですね、彼女にとって」
分院の長が口にした言葉に、オスカーは瞬時に過ぎた時間に引き戻された。少女の眼差しが蘇る。
「・・・馬を用意してくれないか」
ついて出た言葉は、オリヴィエの出した唯一の条件を破ることを意味した。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |