部屋には守護聖3人だけが残った。
「まったく・・・リュミエールは少し融通がきかなすぎるぞ」
オスカーが先ほどの出来事を確かめるように、手をみつめて言った。
「まあ、リュミちゃんもすぐに納得してくれたんだから、そう言わない。本当にありがと、二人とも。彼女にはほんとに良くして貰ったんだ」
オリヴィエはカウチに腰をかけた。普段の彼よりまだ少し顔色が悪いようにも見えた。
「ここへ来てから、どのくらいの時間が経っているのですか?」
リュミエールがオリヴィエの身体を気遣うように聞いた。
「意識が無かった間が3日なら・・・合わせて10日くらいかな」
オリヴィエは曖昧に答える。
「そんなに。大変でしたね、オリヴィエ」
「ん〜、でも実際のとこ、あんまり意識してなかったから。彼女のお陰でここにいる間は随分ゆっくりさせて貰ったし!今聞かれて初めて考えたよ、そういうこと」
「悠長なことだな。聖地の皆が聞いたら怒るぞ」
「良いじゃない、ここへ来たのだって不可抗力だしー。どんな状況でもポジティヴに考えることにしてんの、私は!」
「それはポジティヴではなく、思慮浅薄というのです」
リュミエールがきっぱりと言う。
「・・・・何そんなに怒ってんのよ」
「怒ってなどいません」
「十分怒ってるぜ?さっきから機嫌悪いな、リュミエール。そんなに今夜一晩世話になるのが嫌なのか?」
「嫌というのでは・・・・」
リュミエールはそれだけ言って言葉を切った。
「まあまあ、リュミちゃん。そんなに不機嫌な顔しないで〜!綺麗なお顔が台無しよ。この星にいるとさぁ、何だか気構えがおっきくなっちゃうのよ。時間にせこせこしたり、そういうのって意味無いな〜とか思っちゃう」
「せこせこしていて申し訳ありませんね」
さして言いたくもない嫌みがつい口をついた。オリヴィエのいつもよりも度を超しているように思える軽薄な調子もリュミエールを苛立たせる。
「しかし、アユンって娘は噂通り美しい。久々に良い目の保養ができた」
「さっすがオスカー、目のつけどころがワンパターン!言っておくけど、妙な手出ししたら承知しないからね、私の命の恩人に」
「明日には別れる運命なんだ、わかってて辛い思いをするヤツはいないさ」
「あんたの言葉なんか信用できないねぇ。ほんとに悪戯に口説いたりしないでよ」
「やけに念押すじゃないか、オリヴィエ。さては惚れたか?」
「瞬間湯沸かしじゃないんだよ、アンタと違って。・・・アユンは天涯孤独で淋しい思いをしてたんだ。気の毒な娘なんだよ」
オリヴィエがふさげた口調から一変して、真面目な面もちになった。今朝方の涙を思い出していたのだ。随分自分は幸福だ、と彼女は言った。泣きながら。無理をしている風には見えなかった、そのことがよりオリヴィエの心を締め付ける。あの涙から彼女の、自身ですら意識していないだろう孤独を彼は知ったのだ。一人ここで、過ぎ去った過去や取り囲む様々なものを愛しながら、そのどれもが彼女の耳に愛を囁くことはない。それでもけして絶望することなく、無意識に自分を奮い立たせ・・・。優しげな風貌の中に光る、気丈さ。そんなものを初めて彼女の中に見た。淋しいという言葉を口に出して言えることは、その実孤独ではないのだ。言う相手、その言葉に耳を傾けてくれる相手がいるということだから。
「それは・・俺達もそれとなく聞いた話だ。運命の恋の落とし子だそうじゃないか。ああ見えて情熱的かもしれんな、親の血をひいて」
「その分野であんたにはかなう人間はいないからご安心」
そういってからかうオリヴィエに、オスカーは答えなかった。
二人の会話をずっと黙って聞いていたリュミエールが、口を開いた。
「アユン・・・彼女、私達と最初に対面したときと、この部屋での印象が随分違いましたね。そうは思いませんか、オスカー」
先ほどから感じている違和感。初対面の時のアユンと、今の彼女では別人と言っても良いほどに違う。
「まあな。あの時は俺達が何者かもわからなかったし、緊張してたんじゃないか?」
「今とて別に、私たちが何者かなどひとつも聞きませんでしたよ」
「私と知り合いだってことがホントだったから信用したんじゃないの?ま、実は私も守護聖だってことは勿論、名前しか言ってないんだけど」
「じゃあ、どこの馬の骨とも知れない行き倒れを何も聞かずに介抱して、そのまんま家に滞在させてるってのか?随分と人好しだ」
オスカーが驚く。リュミエールはますます怪訝な顔になった。
「ただの親切心からなら、かまわないのですが・・・」
クラヴィスの意味深な発言。リュミエールが呑み込んだ言葉を察知した上で、オスカーは言った。
「リュミエールはいつだって考えすぎなんだ。それじゃあ眉間のしわが取れないぞ」
「あなた方のようになれたら、と心底思いますよ」
「まあ、明日になれば帰るんだしさ。心配いらないよ、リュミちゃん。アユンは本当によくしてくれたんだ、このくらいのことで喜ぶのなら、聞き届けてあげたい。私も一人じゃ不安もあるけど、アンタ達がいるなら何が起こっても問題ないさ」
オリヴィエは座った椅子の細工に目をやりながら、のんきに構えている。
そこへ先ほどの使用人が、オスカーとリュミエールを呼びに来た。二人はいったん引き上げることにした。
「オリヴィエが見つかったことを連絡に行かねばなりませんね」
リュミエールがオスカーに同意を求めた。
「そうだな。皆心配してるし。汗を流して一息ついたら」
彼らがここへ乗ってきた、小型の高速飛空艇に通信機能がある。二人はオリヴィエには待っているように言って、使用人の後について部屋を後にした。
「・・・なぁ、リュミエール」
飛空挺への道すがら、オスカーは話しかけた。
「聖地に、民を連れていって一緒に暮らす、なんてのは無理なことなんだろうな」
「オスカー、あなた何を・・・!」
リュミエールは驚いて言った。
「まさか、アユンにそこまで?もう?」
確かに彼女は美しかったが、それにしても早すぎる。
「言っておくが俺じゃないぜ」
「あ・ああ・・・そうですか。・・・え?ではオリヴィエが?」
「お前にしては鈍いじゃないか。水晶の予言に気を取られて気付かなかったか?あれ、どうみてもそうだ」
どうみてもそう、と言えるほど明確な意志表示は無かったように思えた。しかし言われて不思議もない。彼の妙に浮き立った態度。あれは本来の気持ちを隠すあまりのことだったのかもしれない。リュミエールは言葉を継ぐことができなかった。
「おそらく彼女の方も。この俺様の手を顔色も変えずに振りほどけるんだ。既に彼女のハートに俺の入り込む余地は無かったってことだな」
「・・・・・それが根拠ですか・・・・」
「いやいや、冗談だ。でもそう考えれば俺達を見て態度が硬かったのも頷けるだろう?オリヴィエと別れたくないんだろうな」
「・・・・別れたくない、と言われても。無理なことです、聖地に連れ戻るなど」
リュミエールはそっけなく言う。
「じゃあ・・・オリヴィエが、帰らないと言ったらどうする?」
「!」
そんな。そんなことが許される訳がない。彼はこの宇宙に唯一無比の夢の守護聖なのだ。聖地にあって女王陛下の為にその身を捧げる者なのだ。
「もしそれが本当ならば哀しいことですが、諦めてもらうしかない。我々は時には自分を滅しても、この宇宙のために尽力しなければならないのですから」
そういきり立つ水の守護聖を後目に、オスカーは道端の草葉をひとつ引きちぎった。
「そうだな・・・。お前の言う通りだ。あいつもそんなことわかってる筈だ」
青い香りの強いその葉を口にくわえて、彼は少し寂しげな笑みを浮かべた。それ以後二人はずっと黙って歩いた。
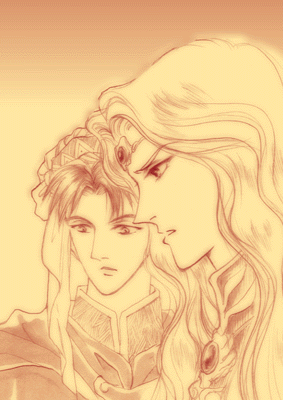 「オスカー!リュミエール!任務ご苦労です」
「オスカー!リュミエール!任務ご苦労です」
スクリーンに大きく映し出されたルヴァがねぎらいの言葉を述べた。他にジュリアスとクラヴィスの姿が見える。二人はオリヴィエが無事見つかったこと、こちらの時間で明朝、聖地へ向けて出立することを簡潔に報告した。
「本来ならばすぐにそちらに向かうべきなのですが。申し訳ございません」
「いえ、こちらにそう急いでいただく訳にはいかないんですよ、実は」
恐縮するリュミエールに向かってルヴァが言った。ジュリアスが続ける。
「クデワタンに隕石が向かっているとの研究院の報告があるのだ」
「なんと!」
オスカーが思わず大声を上げる。「滅びの星」。まさしく予言通りに事が進んでいる。
「まだ何とも言えないんですがねー。軌道がこのままなら明日にでも激突しそうなんですよー。かなり大きな隕石なので、そうなった場合甚大な被害が出るでしょうねー」
呑気な声で大それたことをいう、地の守護聖だった。
「だが案ずるな。陛下と我らの力で軌道は変えられる、さほど大問題ではない。が、そなた達がここへ戻っている暇はない。その地から共に力を合わせることになる。心せよ」
ジュリアスは冷静に言い述べた。
「心配なのは・・・クデワタンの民だ。混乱を招く畏れがある。民に対して有力な力を持つ指導者が必要だ。しかし情報によるとその星は全体を統治する政治的組織など無いようだな」
「はっ。村落ごとに、占いに頼って暮らしているようです。占い師は高い信頼を受けていますが、人々をひとまとめにするほどの力は」
オスカーが報告する。昼間聞いた話がこのように役立つとは思っていなかった。
「では、陛下と守護聖の存在を知らしめ、従わせるしかない」
ジュリアスが言う。
「短い時間でどれだけ民が信ずるか・・・・逆に混乱を招くことになるかもしれんな」
それまで静観していた闇の守護聖の呟きに、ジュリアスの眉根が寄るのがスクリーンを隔てた二人にもわかった。
オスカーとリュミエールは思い出した。神の子の出現。その者こそ、この星の導き手。
「『神の子』ですか。そのような言い伝えが。ふむ・・・、めぼしい人物はまだわからないのですね?これ以後のクデワタンの発展にもそういった人は必要なのですけどもねー」
女王の声を聞き、星を具体的に統治し、導く者。並大抵の人物では無理だ。
「・・・オリヴィエかもしれない」
ふと漏れたオスカーの言葉に一同は息を呑んだ。
「何を申す、オスカー!一時のことではない、今後もその星を導いていく者なのだぞ?守護聖であるわけがない」
「この星にオリヴィエが吹き飛ばされたことの原因は?わかったのですか?」
「・・・・・・」
「この星に既に陛下の声を聞ける程の者がいるのなら、これまでに既にその力を発揮していてもおかしくないのでは?」
「危機に瀕し急に力が目覚めるということもある筈です!」
リュミエールが打ち消すように激しく反論する。オスカーは黙り込んだ。
「リュミエールの言う通りだ、オスカー。軽率な発言は許さぬ」
ジュリアスの言葉にオスカーは頭を垂れた。
「・・・何か・・・あれに兆候でもあるのか」
「クラヴィスまで!何を言っているんですか。オリヴィエがもしそうだとして、クデワタンを導く為には聖地からでは無理なのですよ?星を救うに守護聖ひとりを差し出さねばならないなんて、そんな。過去に前例も無いですしー」
ルヴァがおろおろしている。しかしオスカーとリュミエールは、彼を落ちつかせる術を持たなかった。兆候・・・・。先ほどの話題が二人の頭を支配していた。
取りあえずその話題より隕石の軌道を外すことが先決だった。黙っていれば明日にはこの星に当たってしまう。彼らは今後の綿密な打ち合わせに入った。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |