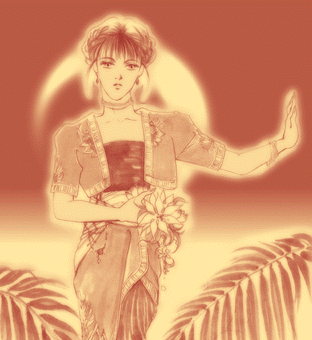二人はなかなか戻らなかった。全員で留守にする程のことではないと、一人この家に残ったオリヴィエだったが、いささか心配になる。何事か起こったのだろうか。胸騒ぎはするが、ここで待っているしかない。
この星での最後の、夜。オリヴィエはそっと庭に出た。この数日ですっかり馴染んだこの庭。もう歩くこともない。彼は少し歩き回ってから立ち止まり、空を見上げた。月が光っている。美しい夜だった。
背後の茂みが音を立てた。振り返る。アユンだった。月の光を受けて、まるで彼女自身が発光しているようだ。彼女の方もオリヴィエが庭にいると思っていなかったのだろう、驚いた顔をしている。
「オリヴィエ・・・・ここにいたの」
「月があんまり綺麗だからねぇ」
二人はそれ以上何も言わず、黙って近くの芝に並んで座って月を眺めた。
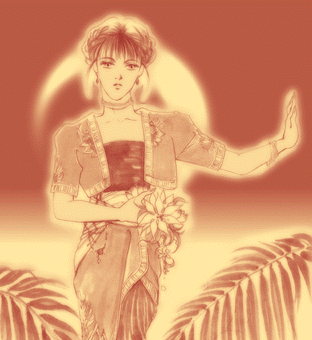
「明日にはさよなら、だね」
オリヴィエが沈黙を破った。しばし彼女が唇が何か言い出すのを待っていたが、アユンは黙ったまま、月から視線を動かさなかった。仕方なく彼は続けた。
「・・・でも、また来ることもあるかもしれないし」
嘘が口をつく。多分、もう二度とこの星に来ることはないだろう。あったとしても・・・・その時に、アユンはおそらくいない。わかりきったことだった。何故自分はこんなその場しのぎを言うのだろう。言い逃れは好きではない。筈なのに。
「アンタに会えて嬉しかったよ。本当に楽しい時間を過ごさせてもらった。何か心から休まったよ、ここでの数日。ありがとね」
言いたいことはこんなことじゃない。それは何かわからないけれど、違うということだけは確実に感じていた。しかし気持ちとは裏腹に、言えば言うほど空々しく響く自分の言葉を、オリヴィエは他人のように聞いていた。
「あなたは・・・・帰ってまた明日からいつも通りの生活に戻るのね」
アユンが表情を変えずに独り言のように呟いた。
「え?あ、そうだね、あんまり考えたくないけど。ここは楽しすぎたよ」
オリヴィエは少しでも場を明るくしようと、笑った。
「あなたを探しにきたあの人たちと一緒に、あなたを今も待っている人たちの元へ」
「見飽きた面々だけどね」
「・・・・・・会いたくなかったわ。私はオリヴィエ、あなたと」
彼女は黒い瞳をまっすぐに向けてオリヴィエを見据えた。
「明日がわからないから良いなんて、慰めでしかないわ。昨日より今日を愛するなんて言い訳だわ。今日が素晴らしかったのなら、それが永遠に続けばいい。時が止まればいい。そう思っても仕方がないから、みんな自分をなだめごまかしているのよ」
その瞳は変わらずオリヴィエを向いていたが、彼女は自分に対して言い聞かせているようだった。怒りとも悲しみともつかぬ感情が、言葉がいくに従って彼女の中で強まって形良い唇から吐き出されていく。オリヴィエには何も言うことができなかった。オリヴィエ自身・・・・彼女と同じことを考えている。この夜が明けなければいい、と。そんな風に思ったのは初めてだった。
彼女は続けた。彼女の瞳はもう誰のことも映していない。
「私は、あの人たちが来た今日より、あなたと二人きりだった昨日のほうを愛する。最初から別れる日が来るのがわかっていたあなたと出会ったあの日より、あなたを知らず、でも父とここで暮らしていた昔のほうを愛する。父と二人きりだった昔より、父と母と赤ん坊だった私が暮らしていた、記憶にすら無い、でもきっと幸せだったろう過去のほうを愛する」
自分が現れなければ、いずれ彼女自身の幸福な未来が気付かぬままの孤独を忘れさせてくれただろう。自分はそんな彼女に、わざわざ孤独を知らせに来た使者なのか。そんな思いがオリヴィエを過ぎる。それは彼にとって酷く辛いことだった。しかし仕方がない。時間は戻せない。今だけだ。彼女が辛いのは今だけだ。そう自分に言い聞かせた。
「父だってああ私には言っていたけれど、本心ではわかったものじゃないわ。私を見る度思っていたかもしれない。母を失ったのはこの娘のせいだって。いえ、もしかしたら、自分が一時の恋を引き返せなかったのは、この娘がいたからだ・・・・」
そのくだりに、オリヴィエは耳を疑った。彼女から聞かされていた幸福そうな彼女の父の姿が歪み形を変えていく。言葉には力がある。口にしたことだけが残り、それがいつのまにか真実となって記憶されてしまう。それ以上はいけない。感情に任せて歪めてはいけない。彼は焦った。彼女を止めなければ!
次の瞬間、アユンは黙った、いや、黙らされた。オリヴィエの唇によって、その口を塞がれて。身体はいつのまにかオリヴィエの腕に縛られ、身動きがとれない。それでもアユンは渾身の力をもって身を離す努力をした。ふと彼の腕がゆるんだすきに、彼女は彼の頬を打った。その反作用で身体が離れる。
「あ・・・・・ご・・」
頬を打たれて初めて自分がしていることに気付いた。目の前にいる娘は、その大きな瞳を見開いて、怒りなのか嗚咽なのか身体を震わせている。風がふたりの間を吹き抜けた。
アユンは振り上げたままだった手をゆっくりと下ろし、言った。
「・・・・謝らないで」
彼女は毅然とした態度でオリヴィエを向いた。
「そうさせたのは私・・・・物乞いのように貧しい心根であなたの同情を買った、私の方なのだから」
「いや、違う、それは・・・」
「いいのよ、オリヴィエ」
彼女は無表情に続けた。
「でもこの星には挨拶がわりにそんなことをする風習は無いの。馬鹿な私が勘違いする前に、あなたはもう行って」
「アユ・・」
「行って!」
すべてのことを拒絶する、叫び。これ以上何か言うことは、許されないような気がした。彼女の誇りを傷つけないために。オリヴィエは行きかけて、また振り返った。
「アユン。ひとつだけ言っておくよ。私の星でも、口づけを挨拶かわりにする風習はないよ」
うつむいていた彼女は、その言葉に顔を上げ、言った。
「・・・・それなら残念ね。あなたが私にしたことが、口づけでなくて”口封じ”だったことが」
宵闇の中に薄く発光しているように輝く彼女の姿はまるで、月の女神のように近寄り難かった。
部屋の近くまで来ると人の話し声が聞こえた。リュミエールとオスカーが戻ってきているらしい。オリヴィエは足早に声の方角に急いだ。茂みの陰から現れた彼を、二人はいち早くみつけて声をあげた。
「ああ、オリヴィエ!庭にいたのか。・・・大変なことになったぞ」
「大変なこと?」
怪訝な顔をするオリヴィエに、二人はオリヴィエに関する部分は伏せたまま、さっきの会談の内容をかいつまんで話した。
「古い言い伝え・・・・そうだ!ここの家に古い書物がある書庫があるんだ。そこに何か詳しい文献があるかもしれない」
「それは好都合です。さっそく言って調べさせて頂きましょう。事は急ぎます。三人いればなんとか探せるかもしれない」
リュミエールは素早く反応した。「神の子」がオリヴィエである筈がない。そう確信したかった。
三人はテユを呼び書庫の場所を聞いた。順序は逆だが致し方ない。本来承諾を得るべきアユンには、テユに言付けを託して先を急いだ。
ルヴァが見たら歓喜の声を上げそうな、古い書籍の山だった。個人の蔵書としては見事なものだ。しかし感心している場合ではない。三人は手当たり次第に本を繰った。しばし黙々と作業は続けられた。
ふと、オリヴィエは部屋のはじに木の机が置かれているのを見つけた。アユンの父のものだろうか。歩み寄り見ると、引き出しがある。手をかけてみると鍵がかかっていて開かない。何か予感がした。オスカーとリュミエールに声をかける。
「古い机だな・・・・このくらいなら何とかなるかもしれん」
オスカーが力一杯取っ手を引っ張った。めきっと木目が割ける音がして、引き出しが開いた、というより壊れた。
「あ〜ああ、あとでアユンに謝っておかなきゃだわ・・・」
そう呟きながら開けられた引き出しの中を確かめるオリヴィエの目に、一冊の古い日記帳が映った。中を見る。アユンの父のものだった。
「日記だ・・・アユンのことが書いてある」
彼女の幼い頃の様子などのくだりを読みながら、オリヴィエは目を細めた。そして手が止まる。彼の顔色が変わったのを、二人は見逃さなかった。
「何か書いてあるのか?」
オリヴィエが指さした先には、アユンの”頭痛”についての記録が残されていた。
アユンは幼い頃から、夜中に目覚めては意味不明のことを言ったりしていたという。アユンの父は最初は気にもとめなかったが、何度も続き、その内にその内容が荒唐無稽ながら筋を持ち出したことに気付いたらしい。おとぎ話のような、聞いたこともない単語を次々に言う娘に、彼は専門家を呼び彼女に催眠療法のようなものを施した。そのころもう自分の命に先が無いと知って、娘の先行きに不安を覚えたのだろう。悪戯に人に触れ回って変人扱いされる事も考えられる。彼は専門家の力を借り、彼女の夢を封じた。しかし、後遺症としてアユンは偏頭痛に悩まされるようになった。日記で彼は最後まで迷っていた。頭痛に苦しむことと、「聖地」「女王」「守護聖」などと口走り人に疎まれることのどちらがアユンにとって幸福だったかを。
「・・・・・・・アユンだったとはな・・・・・・・・・・・」
オスカーが呟く。
「彼女こそ、女王陛下の声を聞き、この星を導く神の子・・・夢を介在として女王陛下のお力を知ることのできる才があったのですね。封じられていたとは、わからない筈です」
リュミエールも意外な結果に驚きつつも言葉を加える。
「あの娘、私が来てから頭痛が酷くなったって言ってた。アンタ達が来る直前はそのせいで意識を失う程だった。テユがこんなことは初めてだって慌てていたっけ・・・。私達のサクリアが彼女の無意識に影響してたんだね・・・」
オリヴィエが言う。彼が一番この結末に呆然としていた。
「滅びの星の到来もきっと関わっているのでしょう」
リュミエールがそう言った、その時、背後で物音がした。一斉に振り向くと、そこには言付けを聞いて後を追ってきた、アユンがいた。
「何を言っているの?サクリア?滅びの星??あなた方は・・・・何者なの!?」
同時に彼女は床に倒れ込んだ。オリヴィエが咄嗟に抱き留める。既に意識が無い。
「急ぎましょう、オリヴィエ、オスカー!とにかく聖地と連絡を取って、彼女の封印を解かなければ!」
彼らは飛空挺へ急いだ。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |