「こちらで今しばらくお待ちください。今、主人を呼んでまいります」
その屋敷の使用人であるらしき大柄の壮年の男が、無表情のまま頭をたれ、部屋を出ていった。部屋、といっても大理石のタイルが敷き詰められた床に太い柱が立っていて、茅葺きの屋根がむき出して乗っている、東屋のような場所だ。オスカーとリュミエールは、言われるがまま所在なくそこで座っていた。
この屋敷は広い敷地の中に、小さなヴィラが点在している作りになっていた。彼らのいる場所からも、緑の合間にいくつか見える。それにはほとんど壁も扉も無いようだが、高床なので外から中は見えない。生い茂る背の高い緑もプライベートを仕切るに一役買っていた。おそらく気候のせいなのだろう。暑さを逃れ出来るだけ風を取り込むのに、大きな屋敷は向かない。扉や壁で区切るより、部屋自体を独立させる方が効率的なのだ。
とても静かだ。時折鳥の声が響くくらいで、後は音ひとつしない。これだけの広い場所にほとんど人は住んでいないらしいのだから、当たり前と言えば当たり前だった。
二人はすることもなく、辺りを見渡していた。数は多くないものの、さりげなく置かれた調度や置物は、この星の美術に詳しくない二人の目からも一見して上等の品だとわかった。しつけの行き届いた使用人を使っているということからも、この家が先ほど会った人々などとは身分や家柄が違うといったことがうかがえた。代々続く名家だったと聞いた。おそらくこの場所ではその昔は、人が賑わい歌舞音曲で溢れる、華やかな宴が催されたりしたのであろう。広いだけに今のように人がいないと、ことさらにうら淋しい。
時が経った。出された茶碗はすっかり乾いている。
「随分もったいぶるな」
「何をもったいぶってるというのですか。・・・あなたという人はほんとに・・・」
オリヴィエ云々よりも格段の美人に会えるということで勢い込んできたオスカーには、待たされているというより、「じらされている」というのが実感らしい。リュミエールはこの星に来てから何度ついたかわからないため息をまたひとつ、ついた。それにしても、遅いことは確かだ。何事かあったのだろうか。
何も察することのできない状況の中、唯一わかることは、おそらくここにオリヴィエはいる、ということだった。二人とは無関係の、この家への客人ということであればこうして待たせるまでもない。得体の知れない訪問者など、追い返せばすむことだった。
「大変お待たせいたしました。私がこの家の主人、アユンでございます」
凛と響く声に二人は顔を上げた。見るとそこには、確かに噂に違わず美しい娘が立っている。まだ若いのに、主人と言うにふさわしい、ある種の威厳のようなものがその声と落ちついた口調、言葉遣いから感じられた。立ち居振る舞いも毅然としていて、彼女の美しさを引き立てている。が、その顔色は酷く悪く、立っているのも辛そうなのことが誰の目にも明らかだった。
二人は立ち上がり、軽く頭を下げた。
「不躾にお伺いしまして申し訳ありません。私達は・・・」
「事情は既に使用人から聞いております」
リュミエールの言葉は娘によって容赦なく断たれた。あまりのきっぱりとした口調に、リュミエールとオスカーは面食らった。何か、彼女の態度は非常に堅い。
口を継ぐことができなくなったリュミエールは、困惑しながら彼女の様子を伺った。視線が合うのを避けるように、その眼差しは微妙に揺れている。そして・・・良く見なければ気付かないほどかすかに、彼女の手は震えていた。
「もしかしてお加減がお悪いのでは。大丈夫ですか?」
リュミエールが彼女の側により、手を差し伸べた。彼女はその手を無視した。
「お気遣いは結構ですわ」
体調のあまりの悪さに余裕が無いのか、語気にはきついものが混じる。
「申し訳ありませんが、掛けさせていただきます。あなた方もどうぞお掛けに」
身元も知れない急な訪問者を大袈裟に歓待してくれるとは思っていなかったが、それにしてもこれほど硬化した態度でなくても、と二人は思った。初見で人を脅かすほど、特異な風貌では無い筈だ。それを証拠に先ほどの店ではああまで皆、てらいなく話しかけてくれたではないか。
そんな思索を絶つようにアユンが再び口を開いた。
「人をお探しとか。確かに今、私どもはお客人をお迎えしております。お仲間の方かどうかはわかりませんが」
「やはり!ぜひ、会わせていただきたい。実際に会うのが一番話が早い」
オスカーが逸る気持ちを率直に伝える。彼は既に腰を浮かせかかっている。
「・・・・・・・・承知いたしました。後をついていらしてください」
いささかのためらいがあったように、二人には思えた。しかし、オリヴィエかどうかを確認することが今は先だ。妙な態度の女主人の後を、二人は追った。
「アユン!もう大丈夫なの?歩き回るなんて無理をしちゃ駄目じゃないか」
オリヴィエはアユン姿を目にするなり声をあげた。労るようにアユンの肩を抱く。
「私はもう大丈夫。それよりオリヴィエ、あなたに会いたいという方達が・・」
彼は背後の戸口に目をやった。物陰に二人。
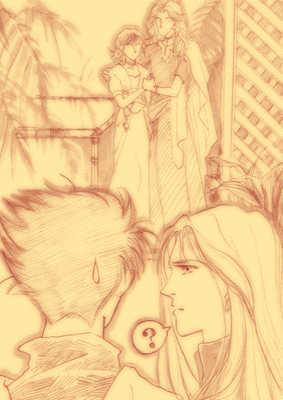 「・・・オスカー!リュミエール!!!」
「・・・オスカー!リュミエール!!!」
「オリヴィエ!無事だったか!」
「お元気そうで何よりです」
三人は一様に、歓喜の声を上げて再会した。
「何だか久しぶりだね〜」
その言葉にオスカーとリュミエールはつい黙ってしまった。二人にとっては一日ほどしか経っていない。聖地とこの星では時間の流れ方が違うのだ。オリヴィエもすぐに気付いて少し複雑な表情をした。
アユンはずっと、黙って彼らを見ていた。心ここにあらずといった様子だ。
「アユン、この二人、私の友人なんだ。こっちがオスカー、それからリュミエール」
オリヴィエは軽く彼女に紹介した。声をかけられて初めて、アユンは我に返った。
「あ・ああ・・・。お探しの方が見つかったようで、本当にようございました、お二方。これでご安心でございますわね」
二人に向かって、彼女は微笑した。アユンの顔に表情らしい表情を見たのは初めてだった彼らは、またもや面食らった。その微笑みは、横にいる美を司る守護聖が一瞬陰をひそめるほど、人を魅了する力があった。
「どうしちゃったのよ〜二人とも。鳩が豆鉄砲食らったみたいな顔しちゃってー。私が無事だったんで安心して気がぬけちゃったのかなーあ?」
オリヴィエがおどけた調子で言う。予想のつかないトラブルで見知らぬ星に飛ばされ、無事に戻れるかどうかもわからないといった状況にあって、何一つ変わってない夢の守護聖。二人の心中には感心と呆然が同時に湧いた。
「お前、ほんとに神経が太いな・・・」
オスカーの言に悪びれるでもなくオリヴィエは答えた。
「アンタ達が心配してるだろうなってことは私にだってわかってたさ。でっも〜こっちからどうすることもできなかったしさ。お迎えがくるまで暗く沈んで待ってるのなんて性に合わないの」
アユンが言葉を挟む。
「でも、こんなに嬉しそうなオリヴィエを見るのは初めてですわ。そうは言っていてもどこか心許なかったのでしょう?身体の調子も思わしくなかったし」
「身体?」
リュミエールが聞き返す。
「ええ、オリヴィエがこの屋敷の庭に行き倒れていたのをお連れしてから三日ほども意識がありませんでしたわ。こうまで元気になったのはここ数日のこと」
「そうでしたか・・・。それは・・・あなたにはなんと感謝を述べたら良いのかわからないほどです。ありがとうございます」
リュミエールはアユンに丁寧に礼を述べた。
「しかし復調しているのなら好都合です、すぐ支度をして・・・」
聖地をそう長く留守にすることはできない。時間の流れが違うとはいえ、早いにこしたことはない。
「まあ、そんなにお急ぎにならなくても!この屋敷がこのように華やかなお客様をお迎えするのは久しぶりなのです、お部屋の支度をさせますから、お二方とも今しばらく・・・」
アユンが引き留める。
「お気持ちは嬉しいのですが、これ以上お世話になる訳には参りません。きちんとした御礼は後に使いの者をよこします故・・・・」
リュミエールは角が立たぬよう、しかしきっぱりと断った。何か胸騒ぎがする。クラヴィスの水晶球のこともある。この星にあまり長くいたくはなかった。
「いいえ、いいえ!まだオリヴィエの身体も完全に癒えているとは言えません。どうか私の願い、聞き届けてくださいませ。大したもてなしなどできませんが、どうか、今夜一晩だけでも」
アユンは、懇願の瞳をリュミエールでなくオスカーの方へ向けた。そのような瞳で見られてはこれ以上強く断れないのが、この男だった。
「・・・こうまで言ってくれてるんだ、一晩くらい良いじゃないか、リュミエール」
「オスカー!皆待っているのですよ?」
「うーん、心配させてるのはわかってるけどぉ〜・・・・。一日くらい大目に見れない?リュミちゃーん」
オリヴィエもリュミエールの説得に当たる。
「しかし」
「あんた達もさ、たまには違った場所でのんびり息抜きしたくない?お説教マニアとかぁ、真っ暗魔人とか、茶飲みじーさんとか、小うるさいガキどもがいないとこで」
「誰のことを言ってるんですか!」
「思いの外早く見つかったんだ、一晩くらい当初の予定のうちだろう?どうとでもなる。これほどの美女の懇願を無碍にするなんてのは男じゃないぜ」
オリヴィエとオスカーのこれらの発言は、リュミエールを静かに怒らせるに十分なものだった。が、今の状況で、無理矢理に自分の意見を押し通しては親切に介抱までしてくれたアユンに対しあまりにも失礼だ。折れるしかない。
「・・・・ほんっとにあなた方は・・・・」
その先の言葉を呑み、リュミエールはアユンに向いた。
「では本当に申し訳ありませんが、一晩だけ。一晩だけ、お世話になることにいたします。過度なもてなしはこちらから遠慮させていただきます。そうまでしていただいては立つ瀬がありませんから」
「まあ、ありがとうございます!リュミエール様、オスカー様。さっそく支度を急がせますわ。私のことはアユンと呼び捨てになさってください。オリヴィエと同じように」
「なら俺達のことも、呼び捨てにしてくれてかまわないぜ?オリヴィエと同じようにな」
オスカーがとびきり気障な笑顔と共に言った。彼の手はすっかりアユンの手に重ねられている。
「始まった始まった〜!アユン、気を付けてね、こいつこーゆーヤツだから!」
オリヴィエが即座に見とがめて忠告する。しかしアユンはさして動じもせずに、嫣然と微笑んでいる。
「本当に楽しい方達。・・お部屋の用意が出来次第、呼びにこさせます。それでは私はこれで」
さりげなくオスカーの手をふりほどき、アユンは部屋を出ていった。その後ろ姿を、彼らは三人三様の面もちで見送った。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |