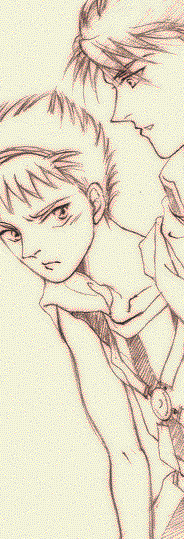
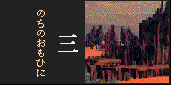
「今頃どのへんかな?あの二人」
風の守護聖ランディが、無邪気に空を仰いだ。どこまでも青く澄み切った空には雲一つない。
「バーカ、見えるわけねーだろ!ほんとにお前って頭たりねーのな!」
鋼の守護聖ゼフェルがからかう。
飛空都市は何一つ変わりないが、アンジェリークとオリヴィエがいないというだけで、何となく物足りない気がしている。ランディとゼフェルは庭園で暇を持て余している風だった。
「おやおや、喧嘩はやめてくださいよー」
そこに地の守護聖ルヴァが呑気な声をあげた。見ると珍しく炎の守護聖オスカーと一緒だ。
「ルヴァ様、オスカー様。ご一緒とは珍しいですね!」
ランディは二人に向かって声をかけた。
「偶然そこで会ってな。若い奴等が二人も揃って公園でひなたぼっこか。何か他にすることはないのか?」
オスカーがからかうように言った。喧嘩っぱやいゼフェルが、とたんに食いつく。
「別に何してようが関係ねーよ!」
「はいはい、別に今日は守護聖としての執務はないですし・・・何をして過ごそうがいいんですよ。日光浴は体のためにも良いことですしー」
ルヴァは仲裁に入ったつもりだが、どうにも間が抜けた感じはいなめない。ゼフェルはこれ以上続ける気がそがれた。
「ルヴァ様、オスカー様。今回のオリヴィエ様とアンジェリークの調査の件なんですけど・・・」
ランディが二人の先輩守護聖に向かって、少し言い難そうに切り出した。
「惑星の状態を実地で調査するなんていう単純な任務に守護聖が同行するなんて話、僕は初めて聞きました。いくら故郷の星だからって、普通じゃないですよね?何か理由でもあるんですか?」
風の守護聖はまっすぐな視線で、一息に言った。
「ああ、あれな。まったくオリヴィエの奴は上手いことやったぜ。金の髪のお嬢ちゃんと旅行なんて。俺が代わりたいくらいだ」
「あんたじゃ女王のお許しは出なかっただろうな」
ゼフェルがさっきの仕返しとばかりにオスカーに言い放つ。
「何だと?」
「まーまー・・・」
困ったような顔をして二人の様子を伺うルヴァ。そして、ランディに向かって諭すように話し始めた。
「ランディがそう思うのも無理はありませんね。通常だったらおそらくは守護聖の同行などなかったでしょう。でも今回は少し事情があるんです」
そう言うと、ルヴァの優しい瞳が少し暗く曇った。言葉を選んでいるようだ。
「事情?」
ゼフェルが聞き返す。
言い難そうなルヴァの様子を察して、オスカーが続けた。
「・・・・女王陛下のお力が、限界をきたしはじめていることはお前達も知っているだろう?ささやかだがその兆しが現れはじめているんだ。その影響は主星から遠く離れた辺境の惑星に色濃い。近いうちに完全に崩壊してしまう惑星もあるのでは、という予測も出ている。アヌーシュカは最も可能性が高いんだ」
「惑星ごと・・・・完全に崩壊・・・・」
若い守護聖達は、予想以上に深刻な宇宙の現状を思い知った。この世界の限界はもうそこまで来ていたのか。
「あー、まだ決まった訳ではないのですけどね。でももし本当に避けられない事態であるなら早急に民の安全な移動など、対策を立てねばなりません。迅速かつ適切な判断を下すには報告書の数値だけでは心もとない。直接確認することが必要と、陛下は判断されたんですよ」
ルヴァは深くため息をついた。それを見たゼフェルはなぜか苛立ち、幾分刺を含んではき捨てるように言った。
「故郷が無くなるかもしれないから、最後のサヨナラしてらっしゃいって訳か?随分おやさしいね、女王陛下は!」
「そんなセンチメンタルな話じゃないんだ、坊や」
オスカーのアイスブルーの瞳が、ひときわ冷ややかに鋼の守護聖をにらんだ。一瞬ひるむゼフェル。
「もし、アヌーシュカが周囲の星々にまで悪影響を及ぼすとなったら・・・崩壊を待たずに女王陛下の手で処理することにもなるんだ。オリヴィエの報告ひとつでどうにでもなるんだぜ?お前にできるか、自分の故郷に冷静に引導を渡すなんてことが」
「ゼフェル。ランディ。これはアヌーシュカに限ったことではありません。少しづつですがそこかしこに既に亀裂が生じているのです。いつ、宇宙全体がそうなるか・・・。女王陛下のお力も、いつまで保っていられるのか。新女王の選定はこの危機に間に合うのか。時間が無いのですよ。失敗は許されません。今回の調査は布石となるとても大切なものなのです」
地の守護聖は哀しそうに言った。
「まあ、勿論あいつが選ばれたのには出身の星だからって理由もあるだろう。でもそれは単に合理的な理由からだ。平常の惑星の状態を知っていた者がいるのは調査にはうってつけだからな」
炎の守護聖も、いつになく真剣な眼差しだ。
「・・・そうだったんですか・・・・」
うなだれるランディ。ゼフェルももう突っかかる様子はない。沈黙する4人。
すっかり暗く沈み込んでしまった雰囲気を何とかしようと、ルヴァが口を開いた。
「あー、でもアンジェリークにはそんなことは知らされていません。あくまでも女王候補としての見聞を広めるため、ということになっています。肩に力が入りすぎるのもよくありませんしねー」
オスカーも高らかに笑いながら続けた。
「あのお嬢ちゃんが今回の任務の真実に気付くことがあったら、女王候補としてはかなりのものだと俺は思うがな。あののんびりさ加減じゃあまり期待できそうにもないな」
「そうですねー、どうでしょうねー」
オスカーとルヴァはそう言うと、ランディとゼフェルに別れを告げ、立ち去った。残された二人は、先輩守護聖の後ろ姿を見据えながら、この宇宙のこと、そしてオリヴィエとアンジェリークのこと、それぞれに思いを馳せた。
|
HOME
|
NOVELS TOP |