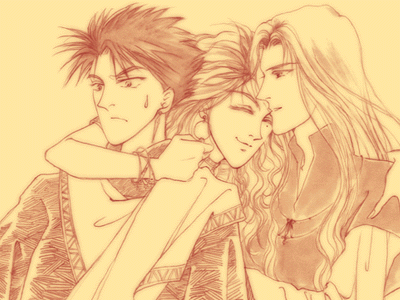オスカーとリュミエールの二人はいつ見えてくるともわからないオリヴィエの姿を待ちながら、彼と別れた時のまま、外に立っていた。
「神の子、というのは実際どの程度の力を持つんだろうな」
「どうでしょう・・・」
隕石が向かってくるなどという大事がそうそう起こるとも思えない。女王の言葉をそのままにその口から人々に伝える、というようなことはおそらくこの先ないだろう。彼女に与えられた命は聖地にいる者にとってはほんの短い間。彼女の「神の子」としての役割は、女王の存在を民に知らしめる、その事が一番の大仕事・・・いや。
「オリヴィエを時空を超えてこの星に呼ぶことがアユンの、神の子としての役割だったのかもしれないな。すべてはそこから始まった」
「そうですね・・・ならばあの二人の強い結びつきも不思議ではありません。彼女が呼んで、オリヴィエが応えた。すべては最初から決められていたこと。この星のために、宇宙のために」
そしてこの星の運命は動き出す。今後彼女はこの星の統治者として女王の意志に従って民を導く。まだ若く、いきなりのこととはいえ、選ばれたからには様々な苦難に打ち勝っていける力を秘めているのだろう。
「この星には、長い間独自で培ってきた宗教理念がありますから、それらを尊重しつつ必要なだけの発展を促すよう、陛下と王立研究院の取りはからいがあるでしょうね」
「空も風も土も石も花にも、・・・か。確かにそれは元より間違っていないからな、聖地の存在もそう受け入れがたい考え方ではないだろう。有形無形すべてのものに、サクリアの恩恵は満ちている。水にはお前、炎には俺の・・・」
そして、夢にはオリヴィエの。人々の心底の望みである、美・愛・楽・自由。それらを司る夢のサクリア。求めるところから、人々は始める。夜毎降りる夢に、人々は理想の明日を見る。
「夢のサクリアというのは、我らの力の中でももっとも人の根元にあるものなのですね」
「指針・・・、道しるべ・・・。何よりも先んじて、常に前に在らねばならない。すべての事はその後だ」
二人は思った。オリヴィエは自分の夢を見るのだろうか。自らの内なる望みに耳を傾けることがあるのだろうか。もしそんなものに気付いた時・・・・彼はそれでもここに戻って来るだろうか。
待っているだけの時間は酷く長く感じられた。
夜が白々と明けてきた。そんな不安が過ぎったその時だった。
「はぁ〜い。お・ま・た・せ〜〜〜〜!」
背後からいきなり素っ頓狂な声が上がった。
「なぁによ、二人ともー。そんなに驚くことないじゃないの」
振り返るとそこには、何も変わらない、いつもの夢の守護聖がいた。彼は笑っている。それを見る二人の顔は複雑だ。彼の清々しい顔とは反対に、安堵と驚きと歓喜と。いろいろな感情が入り交じり躊躇すらしている。
「・・・オリヴィエ・・・待っていましたよ・・・・!」
やっとの思いでそれだけを吐き出すように言うリュミエール。
「やだ、リュミちゃん、何当たり前のこと言ってるのよ〜。そんなに待ちくたびれた?ごめんごめん、意外と時間かかっちゃって」
当たり前のこと。そう、彼がここに戻ってくることは当たり前のことのはずだった。今まではそんなことを不思議と思ったこともなく、彼の存在を享受していた。しかし今は違う。彼がここにいること、それは二人にとっては奇跡のようにも感じられた。
黙ったままのオスカーが、やっと口を開いた。
「置いて行こうと思ってたとこだったぜ。あんまり待たせるな」
「それを言うなら”連れ戻しに行く”でしょ?」
オリヴィエが言葉尻をとらえる。
「はっ、誰が行くか。お前なんかいなくても帰れる」
「オスカー、そんな憎まれ口を・・・」
オリヴィエを気遣ってリュミエールがたしなめる。いつもの、そして何だか随分懐かしい彼ら。オリヴィエは知らず目を細めた。
思い残すことは何もないよう、アユンと別れてきたつもりだった。この二人が与えてくれた猶予によって、ここを離れた時とは、別人のように違っていることは自分が一番よくわかる。今できる最善の選択を、間違いなくできたと思っている。そこに迷いは無かった。
ただ・・・随分と自分が弱い人間であると思い知ったことも事実だ。心に隙ができれば、振り切ったはずの想いに紛れそうになる自分。どこか信用しきれなかった。この先、本当に明日だけを信じていられるだろうか、そう思いながら道を戻ってきた。不意に振り返りそうになる自分を感じながら顔を上げると、彼らの姿が遠くに映った。一瞬その姿がこみ上げるもので歪んで見えた。別れた時と変わらない様子で、待っていてくれている二人。
オリヴィエはオスカーの言葉をもう一度胸に繰り返した。
置いて、行く。
この二人なら本当に、そうしてくれたかもしれない。ここへ戻らないという選択をしても、そのまま何も言わず行かせてくれたかもしれない。
迷ってもいい、振り返ってもいい。それでも待っている、お前が自分でここに戻ってくるのを。そう二人の眼差しは言ってくれているように思えた。そう思うと嬉しかった。
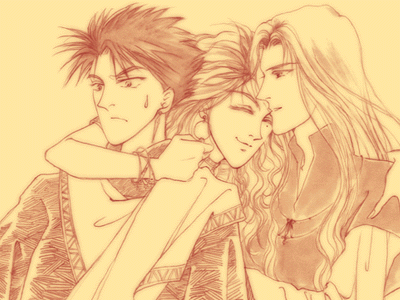
オリヴィエは戯けた調子で言った。
「いいのいいの、リュミちゃん。この男が素直じゃないのは重々承知。長い付き合いだもんね。さあ、帰ろうか、同じくながーい付き合いの、見飽きた面々の元に」
「どれだけ心配かけてると思ってるんだ??」
「わかってるわよーう。でも何度も言うけど、今回のことはワタシのせいじゃないもん。・・ま、帰りが少々遅くなったのには責任あるけど。それだって〜アンタ達にもその責任の一端はあるし〜ワタシには何一つ後ろ暗いところはないもんね」
「そういう罰当たりなこと言ってると、報告するぞ」
「何を?」
オリヴィエはどきりとした。その顔を見て、リュミエールが何食わぬ顔で言った。
「例えば・・・お説教マニア、真っ暗魔人、茶飲みじーさん・・・・などと評していたことですか。お怒りになるでしょうねえ・・・特にお説教マニア・・・」
「いや、こいつに言わせるとマニアなんだから、お喜びになるかもしれないな。もう一昼夜でも二昼夜でも、とことん守護聖としての道を説いてくれるだろう」
「あ。・・・・お願い、それやめて。ね?ね?今度おごるから!それはここだけの秘密ってことにして〜!」
三人は笑い合った。オリヴィエの様子から、少しの無理も感じられない。それだけわかれば、何があったかなど聞かなくてもいい。そう、今はこうして笑い飛ばそう。本当は他にある、三人だけの秘密について。
(終)
|
HOME
|
NOVELS TOP |