オリヴィエは、その両腕をまだ明け切らぬ薄青の空に思いきり掲げて、大きく深呼吸をした。この熱い星で一番、清々しい風の吹くこの時間が彼の一番のお気に入りだった。彼は日頃、決して寝覚めの良い方ではなかったが、ここへ滞在してからこっちすっかり早起きの癖がついた。
目覚めてから既に数日が経ち、彼は元の通り回復していた。
少し庭を歩いてみる。庭、とはいえ小さな密林といっても過言ではない。木々の枝を太い蔓が渡り、長身の彼の頭をかすめる。鬱蒼と茂る葉の隙間から光を得て、朝露に濡れた原色の花々のつぼみが膨らむ。既に開いている大きな一輪を摘んで鼻先にかざした。強い匂いに気が遠くなりそうだ。
日差しはすぐにきつくなる。空はどこまでも紺碧に深く、積乱雲が時折アクセントを添える。太陽がひとたび昇れば、今の過ごしやすさが嘘のような熱気に包まれ、足下から気化した水分が立ち上ってくるのだ。そうして陽が中空を過ぎた頃、熱を冷ますようなスコール。それが止めばまた嘘のように陽射しは照り返し・・・。風が柔らかくなる頃、薄い茜の中に星がひとつふたつと現れて、それを合図に宵闇が忍び寄る。漆黒の闇。ここには中間色はない。いや、色だけではない。香りも光も雨も、その存在を強烈に主張するようにくっきりとその輪郭を他と隔てていた。聖地とはまるで違う・・・何もかもが。
今頃皆はどうしているのだろう。自分がここにいることはもうわかっているのだろうか。それとも。オリヴィエは久しぶりに聖地を思った。長く過ごしたあの場所は酷く遠く、既にぼやけて上手く思い出せないほどだった。ここにこうしている自分の方が、今となってはしっくりくるような気がした。そう長い時間を過ごした訳でもないのに。
「相変わらず、お早いのね」
既に聞き慣れた声が響く。オリヴィエがこうまでこの星でくつろいでいる所以・・・茂みの中から現れた彼女に、彼は振り向き微笑んだ。
「アユン、おはよう。今日も綺麗だね」
「いやだわ、オリヴィエ。この国には、そんな言葉を挨拶がわりにする風習は無いわ」
「挨拶じゃなくって見たまんまだよ。どんなに眩しい陽の光だって跳ね返すくらい」
「私の肌はあなたのように白くはないから、そう見えるのじゃなくて?」
オリヴィエが自分の髪に挿した花を、少し手で直しながら、アユンは静かにそう言って笑った。
そう・・・・肌の色さえ違う。オリヴィエがこの星の人間でないことはどんな子どもにだって一目瞭然だった。しかし、彼女がオリヴィエについて根堀り葉堀り聞くようなことはなかった。聞かれたところで本当の事は言えないが、それでもオリヴィエは少し肩すかしをくらったような気がしていた。当然、聞かれるものと覚悟していたのだ。頭の中でいろいろと嘘のプロフィールを捏造していた苦労は無駄に終わりそうだ。・・・それとも無意識に隠している風に見えていて、それを彼女は敏感に察しているのだろうか。
まあ、どっちだってかまわないけどね。オリヴィエは心の中で一人呟いた。
そう言うオリヴィエもまた、彼女のことをあまり聞かなかった。両親を早くに亡くしているらしいこと、この広い家で一人で世間とは隔絶した暮らしをしていること。会話の中や数日の生活の中でそれとなくわかる以上のことを、彼の方から問いただすようなことはしなかった。彼女が何者であるか、どんな人生を今まで歩んできたか。そんなことはどうでもいい気がしていた。それを知ったところで、今目の前にいる彼女の何が変わるでもない。
ここ数日、こうして庭を歩き、共に緑を楽しみ、お茶を飲み、音楽を聴いて。そんなことばかりしていた。ある時は夜を徹するほどとりとめのない話を、ある時は二人数時間も口をきかずに降る雨を眺めて。皮膚に張り付く汗のように、時間がふっと浮いては消えていく。あまりののろい足どりに、「過ぎる」という感覚を起こさせない時間の流れ方。特別なことは何も起こらない。それとも何も起こらないことが得難い特別なのか。この星の濃密な空気の中で何も考えず、ただ漂うように過ごすのがこれ以上もなく心地よかった。過去も未来もなく、ただ「今」だけが、在る。余計なことは考えたくなかった。いや、その「余計なこと」が何だったのかすら既に二人ともが忘れ果てているような気がした。
朝食を終えて、二人はアユンの部屋にいた。外には静かに雨が降っていた。雨期が近づいているのかもしれない。
「さっきまであんなに晴れていたのにね」
オリヴィエは大きく開かれた窓に腰をかけ、軒からその長い腕を伸ばした。手のひらにぬるい雨粒が当たる。すぐにそれらは手の中で集まり、水滴となって一筋手首を伝った。
窓の正面に位置した椅子に腰掛けながら、アユンは、甘い音楽のように響く彼の声に聞きいっていた。そこからではささやかな音でしかわからない雨のしずくが、まるでこの身が彼の手のひらになったように、感じられるような気がした。
薄雲る空、降る雨、それに洗われてより一層その色を濃くしている庭の緑。そして窓辺に腰をかけ遠くの様子を伺う、大理石の彫刻のような横顔。窓枠を額縁とした一枚の絵のようにアユンには見えた。
細く長いその指先が、鳥の羽ばたきのように流麗な動きで空を仰ぐ。美しく染め分けられた長い髪は腰まで及んで、彼が動く度に衣擦れよりも小さな音を立てさらさらと揺れた。ごく普通の動作のすべてが、彼にかかると目を見張るほど艶やかだ。
彼の元いた場所では、皆がこのように美しいのだろうか。
そう思った途端に、頭が、楔を打ち込まれたようにきしんだ。相変わらずの頭痛。特に、今のように彼について具体的なことを思い浮かべると、鋭く痛みが走る。まるで誰かが自分に何か忠告をしているようだ。どんなに見つめても、手の届かぬ人だと。
わかっているわ、彼を最初に見つけた時から。見えないおせっかいに向かって彼女は一人ごちた。彼の笑顔はてらいないけれど、彼を包む空気は他の人とは違う。見目だけではなく、内から出ずるものが何かはっきりと違うことが、彼女にはすぐわかった。どこか遠い星で、普通なら自分など口をきくのもおこがましい程の高い身分の人かもしれない。そう考えると自然と心が沈む。彼の今までのことを聞かないのも、そのせいだった。
「随分と本がいっぱいあるんだねえ。好きなんだ?本、読んだりするの」
いつの間にかオリヴィエは窓辺を離れ、部屋に置かれた書棚の前に立っていた。彼は一冊を手にとって開き、ページをぱらぱらと繰る。そんなたわいない仕草にもつい目を奪われてしまう自分に気付いて、アユンは慌てて視線をそらした。
「あ、ああ、そうね。本を読むのは好き。他にあまりできることが無いせいもあるけど」
ふと昔読んだ本の内容が過ぎった。貴種流離談。胸躍らせたおとぎ話・・・。
彼は再び本を元あった場所に返し、椅子に腰掛けた。
「ふうん。私は駄目。文字見てるとどーしても眠くなってくるんだよね。たまには詩でも読んで気の利いた言葉でも覚ようかって思っても、気が付くと枕がわりになってる。もう諦めたよ」
二人は共に笑いあった。
「でも、ほとんどは父のものよ。この家にはここの他に一つ、書庫もあるの。古くて貴重な本もあるとかで、そこにだけ扉と鍵がついてるの。子どもの頃は秘密の花園みたいに思えて入りたくて仕方がなかったわ。でも入れるようになってみれば、普通に本が積んであるだけの部屋。少しがっかりした記憶があるわ」
「ふふ、そーゆーもんだよね。鍵をかけたまま大事にしまっておいた方が良かったってことは、この世にゴマンとある。勿論、その逆もあるけど」
「中を見るまでどっちかわからないなんて、あんまりだわ。事前にわかればいいのに」
そうアユンはため息をついた。
「それ、つまんなくない?蓋開けてみなきゃわからないから、面白いんだよ。何が起こるかわからないから、明日にわくわくするんだ」
「父と同じことを言うのね」
父もよく、幼い自分にそう言っていた。代々続く良家の子息として何の苦労もない人生を約束されていた父は、街場の占い師だった母と出逢い恋をした。既に母は自分を身ごもっていたこともあって、身分違いとの周囲の大反対を押し切って結ばれた二人。人知れず辛いこともあったのだろうか、母はほどなく身体を病み、二人の運命の出逢いはそう長い間は続かず終わった。それでも父は、笑ってそう言った。
「昨日より今日のほうを愛している、だから明日も信じられる。日々は繰り返しのようにみえて同じではない、明日には何が起こるかわからない。それを思うだけでいつでも自分は幸福だ、ってね」
「素敵なお父さんだねえ。私も賛成。ついこないだまでは知らない同士だった私達だって、今はこうして楽しくお茶を飲んでる。それだけで昨日より今日を愛せるよ、私も」
「ふふ、そうね。でもおかしいと思わない、そんな彼の好きになった人は、明日を見知る占い師だったのよ?」
「あれ、ほんとだ」
二人はまた、声をあげて笑った。
「でも、お父さんを責めちゃ可哀想。恋心はどんな理屈つけたって止められないもの」
オリヴィエは、そう言いながらオスカーのことを頭に過ぎらせていた。いかにもヤツの言いそうなこと。今頃心配しているだろうね。でも。どうすることもできない。この星はどうやら酷く辺境で、女王や守護聖の存在など露ほども知られていない様子だ。こちらから無事を伝えることは叶わない。何もできない以上、考えても無駄。オリヴィエはすぐに考えを打ち切った。
「あら、こんなところにリュートがある。しかもさりげなく良い細工」
話題を変えようと、部屋を見渡す。隅に立てかけてあった楽器に目が止まった。
「アユン、弾けるの?」
「私は全然駄目。この家に伝わる古いものだから、手入れだけは忘れないようにしてるんだけど、今は誰も弾く人はいなくて・・・。オリヴィエは?弾けるの?」
「楽器はなんでも好きなんだ」
「本当に?ならお願い。弾いてみせてくれない?その音色ももうずっと聞いてない」
「私なんかでよろしければ、姫の望みのままに」
オリヴィエはそっとリュートを取り上げ、再び窓辺に腰掛けた。少しつま弾いて音を確かめてから、おもむろに弾き始める。ひとつひとつの繊細な音が滴のように降り注ぎ、合わさって和音になる。それが幾重にも重なってメロディを形作り、場に満ちた。
アユンは目を閉じる。耳にだけ神経を集中させて、そのどことなく寂しげな異国の曲に聞き入った。様々なイメージが音に誘導されるように頭に浮かぶ。父の顔、母の顔。この部屋から夜毎見える月、星。強い陽射し、涼やかな風。意識したこともない、自分の中に当たり前のようにあった、あらゆるものへの愛を彼女は感じていた。
そこへ突然、張りのある声がさらに重ねられた。まさか歌までつくとは思っていなかった彼女は小さく衝撃を受けた。その歌はとくに歌詞を持たず、ただただ朗々と弦に沿うように響く。楽の音も声も、どちらが強く主張するでもなくバランス良く溶け合わさって、ここにあるすべてのものを包んでは染み込むように消えていった。
曲が終わる。オリヴィエは深くため息を吐いた。
「つい、興がのっちゃって。ねえ、どうだっ・・・」
顔を上げ、アユンに感想を聞こうと彼女を見る。アユンの瞳からは後から後から涙が溢れ、頬には幾筋も跡を作っていた。オリヴィエは慌てた。
「ああっ!ご・ごめん!曲がちょっと辛気くさかったかな・・。泣かせるつもりなんかなかったんだけど・・・・調子にのって歌までつけちゃって・・・なんか嫌なことでも思い出させちゃったかな・・・」
つい、しどろもどろになる。
「いいえ!そんなことないわ!」
アユンは慌てて手の甲で涙を拭い、否定した。
「こっちこそごめんなさい、気がそがれたわね。あんまり綺麗な曲だったから」
「ああ、なら良かった」
「いろいろなことが頭を巡ったわ・・・。私は今も随分と幸福なんだって・・・・そう思えた。どうしてかしらね、不思議。あなたの魔法にかかったみたいよ」
そう聞いて胸をなで下ろすオリヴィエだった。しかし何か気まずい雰囲気がまだ残って、適当な言葉を探しては形にならずに消えていく。少しの間沈黙が続いた。
しばし黙って涙が止まるのを待ってから、アユンは口を開いた。
「本当に素敵だったわ。そのリュートも長い間の鬱憤を晴らしているみたいに良い音をさせて。可哀想なことをしてたわ、私が弾ければ良かったのだけど」
「それなら教えてあげる!こっちへおいでよ」
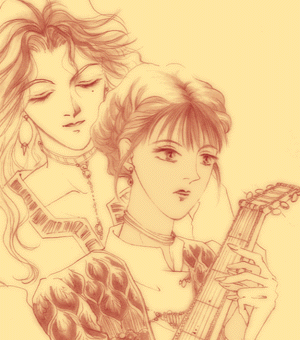 オリヴィエは涙の詫びをしようとばかりに、明るい顔で提案した。彼女を導き窓辺に座らせ、リュートを彼女の手に握らせる。そして背中から腕を回し、彼女の細い指の上に自分の指を重ねた。
オリヴィエは涙の詫びをしようとばかりに、明るい顔で提案した。彼女を導き窓辺に座らせ、リュートを彼女の手に握らせる。そして背中から腕を回し、彼女の細い指の上に自分の指を重ねた。
「ここをこうするとね・・・ほらまずはこの音」
アユンにはもうリュートの音など遠くに聴こえていた。耳元で響くオリヴィエの優しい声。感じる息づかい。紅潮する自分の頬には彼の柔らかな長髪がかかる。絃を押さえる指に力が入らない。この大きい心臓の音は、彼に気取られていないだろうか?
鼓動の音に呼応するように、頭痛がまた一段と強くなった。あまりの激しい痛みに目眩がし、ぐったりと脱力していく自分の身体。遠のく意識の中で、異変を感じとった彼の、自分を呼ぶ声だけが歪んだエコーを伴って響いていた。
つづきを読む
|
HOME
|
NOVELS TOP |
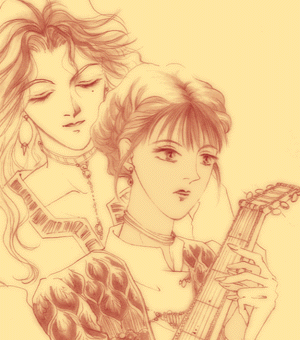 オリヴィエは涙の詫びをしようとばかりに、明るい顔で提案した。彼女を導き窓辺に座らせ、リュートを彼女の手に握らせる。そして背中から腕を回し、彼女の細い指の上に自分の指を重ねた。
オリヴィエは涙の詫びをしようとばかりに、明るい顔で提案した。彼女を導き窓辺に座らせ、リュートを彼女の手に握らせる。そして背中から腕を回し、彼女の細い指の上に自分の指を重ねた。